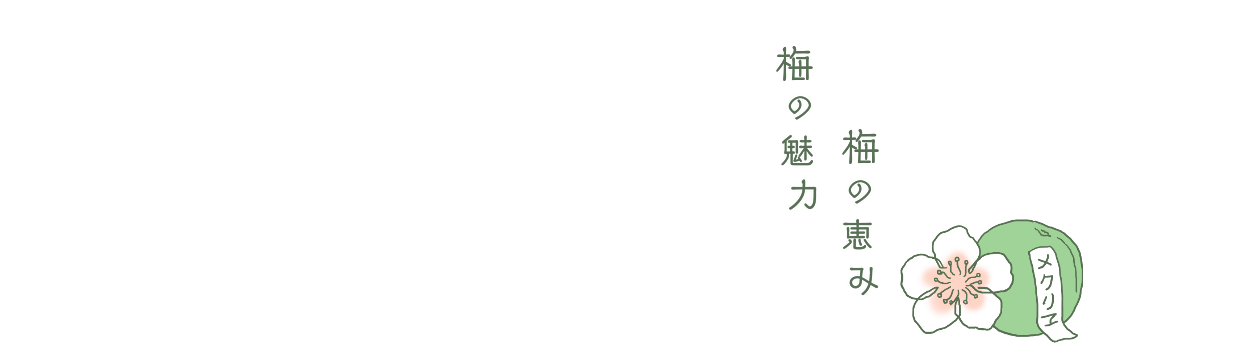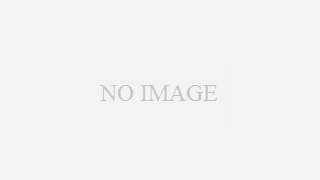春一番に咲くのは梅の花。
「百花魁(ひゃっかさきがけ)」
という言葉があるように、
梅はまだ寒い早春の頃に
他の花より真っ先に咲くといわれています。
忍耐強く花を咲かせるように見える
梅のその姿は、古くから人々に好まれ
愛されてきました。
梅にまつわる言葉は事あるごとにあり、
今でも多くの言葉が使われています。
梅の花咲く早春の頃。
梅の実が大きくなり、色づく初夏の頃。
そして梅雨のころにも。
今回はそんな、梅の言葉について
調べてみることにします。
それでは、いってみましょ^^
梅という言葉
梅はそもそも日本にあった
という説もあるようですが
今のところは、
中国からやってきた
という説が有力のようです。
そしてウメという言葉や
梅という文字にしても、
やはり中国から伝わったということです。
(詳細は別記事にて→ 梅の漢字の成り立ち)
花言葉
梅の言葉というと「花言葉」が浮かびます。
花言葉とは、花や草木に
何かしらの意味をもたせたもの。
このような行いは世界の各地で行われて
いたようですが、ヨーロッパで花言葉
という形でまとまったようです。
しかし人々の思考は各地で異なるもの。
花言葉も同じく、各国で定着するにつれて
それぞれのお国柄が反映されていくのですが
梅については似たイメージを持つようです。
これについて詳細は
別記事に書いているので
よろしければどうぞ→「梅の花言葉」
梅にまつわる言葉
他にも梅にまつわる言葉は、
ことわざや故事、言い伝えや迷信など
多くあります。
梅の木・梅の花・梅の実、梅干しに至るまで
さまざまな「梅」の言葉があるのです。
これらには梅とともに暮らしてきた人々の
思想や信念、教訓などが込められていたり、
生活の知恵や習慣などが現れていたり
するのです。
詳細は下記のリンクからどうぞ~。
・桃栗三年、梅は?
・梅に鶯(うぐいす)ってじつは…
・梅はその日の難逃れ
梅の花と別名
春の行事として「お花見」があります。
そもそも花見というものは、
はじめは桜ではなく、梅であったとか。
今でこそ花見といえば桜ですが、
梅の花見は一味違い、やはりいいものです。
桜は4月に対し、梅は2月~3月が花盛り。
時期的に寒いので
そこが少々ネックではありますが、
桜と決定的に違うのは「香り」
梅の花見へ行くとよくわかるのですが、
辺りをただよう梅の香りはなんともいえず
心地のよいものです。
梅を現すもの
梅の別名は、和歌などで使われている。
特に梅の花の頃。
直接的に「梅」とはいわず、
別の言葉で梅だということをにおわせる。
それは梅自体のことであったり、
梅を表わす比喩であったり、
梅の佇まいを現すものであったりと
多岐に及び、驚くほどの数がある。
次の項で言葉を一通り紹介しますが、
和歌や俳句、茶などを嗜むか方には
馴染みのある言葉もあるでしょう。
まったく疎い私には
初めて見る表現がとても多く、
その字の並びを見たところで
検討もつかない言葉も多くありました。
春先に梅があり、梅が芽吹き、
梅の花が咲くというその状況について
これだけの言葉がある。
昔の人はなんて表現が豊富なんだろうかと
感心するばかりです。
梅の別名
梅の別名のみならず、梅を現した言葉について
調べられたものだけを次に記載します。
| 梅の別名・異名 | ||
| 梅早花 | うめつさばな | |
| 香栄草 | かばえぐさ・こうばえぐさ | |
| 香雪 | こうせつ | |
| 木花/木の花/此の花 | このはな | |
| 清友 | せいゆう | 名花十友(めいかじゅうゆう)に由来する。 |
| 君子 | くんし | 梅は四君子(梅・菊・蘭・竹)のひとつ。 |
| 君子香 | くんしこう | |
| 氷花 | ひょうか | |
| 清客 | せいかく | |
| 雪魂 | せっこん | |
| 雪中君子 | せっちゅうくんし | |
| 雪中高士 | せっちゅうこうし | |
| 初花草 | はつはなぐさ | |
| 花兄/花の兄 | はなのあに | |
| 花待草 | はなまちぐさ | |
| 氷魂 | ひょうこん | |
| 木母 | もくぼ | 梅を分解した言葉。木公を松とするのと同じ。 |
| 藻塩草 | もしおぐさ | 他にヤマブキ・アマモ・シバナの別称でもある。 |
| 雪君 | せっくん | |
| 逸民 | いつみん | 俗世を離れて住んでいる人。 |
| 花魁 | かかい | 梅の別名にして蘭の別名であり蓮の花のこと。 また、遊女。 |
| 花儒者 | はなじゅしゃ | |
| 朽木 | くちき | |
| 玉骨 | ぎょっこつ | 貴人・美人の骨、梅の幹枝をたとえる言葉。 |
| 玉蘂 | ぎょくずい | |
| 孤山 | こざん | ただ離れてある山。 |
| 好文木 | こうぶんぼく | 学問に勤しむと梅の花が咲いたことから。 |
| 香散見草 | かざみぐさ | |
| 春告草 | はるつげぐさ | |
| 初名草 | はつなぐさ | 寒梅の異称。 |
| 世外佳人 | せがいかじん | 世外とは、俗世間をはなれたところ。俗世を脱した境遇。佳人とは、美しい人。 |
| 匂草 | においぐさ | |
| 百花魁 | ひゃっかさきがけ | |
| 風待草 | かざまちぐさ・かぜまちぐさ | |
| 緑花 | みどりのはな | |
| 杣婆 |
以上ですが、まだ他にもあるようです…!
梅雨にまつわる言葉
「ツユ」あるいは「バイウ」という言葉は
何故、梅の雨と書くのか。
梅雨の文字
梅雨という文字が使われるのは、
梅の実がなる頃だからという説があり、
梅の実が黄色く熟す頃なので
黄梅雨(こうばいう・きつゆ)とも書く。
また、ツユはジメジメと湿気が籠もり
黴(かび)の生えやすい時期の雨なので、
黴雨(つゆ・ばいう)と書く字もある。
これらの漢字は古くから中国で使われて
おり、日本へもそのまま伝わったのでは
ないかということです。
黴雨の頃…というと
じつに嫌な季節だと思いますが、
梅雨の頃…というと
何故かそんなに悪くもない気がします。
字面としても「梅雨」と記すのが美しい。
ちょっとしたことですが、
生活する上では少しでも気楽なほうが
いいですよね。
梅雨の言葉
梅雨の言葉について調べてみると、
梅雨どきに使われる言葉がいくつか
ありましたので紹介します。
| 梅雨にまつわる言葉 | ||
| 梅雨/黴雨 | つゆ | 梅の実が熟す頃に降る雨。または黄梅雨とも書く。 カビが付きやすい時期の雨。 |
| 入梅 | ついり・にゅうばい | 雑節のひとつ。 |
| 梅雨入り | つゆいり | 長雨の時節。入梅。 |
| 梅雨明け | つゆあけ | 出梅(しゅつばい) |
| 梅天 | ばいてん | つゆぞら。 |
| 梅霖 | ばいりん | 梅雨。さみだれのこと。 |
| 走り梅雨 | 梅雨の前触れに雨が続くこと。 | |
| 空梅雨 | からつゆ | 梅雨の間に雨が少ないこと。てりつゆ。 |
| 菜種梅雨 | なたねつゆ | 菜の花が咲く3月下旬から4月上旬の頃の長雨。 |
| 山茶花梅雨 | さざんかつゆ | さざんかが咲く11月下旬から12月上旬ころの長雨。 |
| 五月闇 | さつきやみ | 梅雨の時期の夜の暗さ。またそのくらやみ。 |
| 五月雨 | さみだれ | 梅雨。さみだれ。 |
| 五月晴れ | さつきばれ | 梅雨の間に見られる晴れ間。 現在では5月のよく晴れた空のこと。 ※今と以前とで意味合いが異なる。 |
| 黒南風 | くろはえ | 梅雨初めの暗い空に吹く南風。 |
| 荒南風 | あらはえ | 梅雨の中盤ころの強い南風。 |
| 白南風 | しろはえ | 梅雨が明ける頃に吹く南風。 |
後半の言葉は
梅の字は入っていないのですが、
梅雨にまつわる言葉なので
入れておきました。
雨というのも一言で「雨」で済むもの。
しかしどんなときに降る雨なのかという
違いにより、表現はさまざまに
あるものですね。
月の異称
梅の名が付く月がある。
それは梅の花の頃だったり、梅の実の頃。
これらの言葉は
「梅ありき」で季節を表現したもの。
梅と名の付く月の異称には、
次のようなものがあります。
| 月の異称 | ||
| 梅見月 | うめみつき・うめみづき | 陰暦2月の異称 |
| 梅つ五月 梅津五月 梅津早月 |
うめつさつき | 陰暦2月の異称 |
| 梅つ月 梅津月 |
うめつつき・うめつづき | 陰暦2月の異称 |
| 乾梅 | けんばい | 陰暦4月の異名 |
| 梅月 | ばいげつ | 陰暦4月または5月の異称。 |
| 梅の色月 梅色月 |
うめのいろづき | 陰暦5月の異称 |
| 梅夏 | ばいか | 陰暦5月の異称 |
| 梅天 | ばいてん | 陰暦5月の異称 |
| 紅梅月 | こうばいづき | 陰暦9月の異称 |
| 梅初月 | うめはつづき | 陰暦12月の異称、梅が咲き始める頃の月。 |
ここでは「梅」を含んでいる
月の異称だけを紹介しましたが、
他にも山ほどの数があるので驚きです。
興味のある方はググってみてくださいな。
後記
さて今回は、梅にまつわる言葉について
調べてみました。
梅の言葉。
梅の名の付く言葉は
けっこうあるものですね。
昔は暮らす環境やら地域によっての差
などが現代より多くあったでしょう。
言葉の表現も違えば少々意味が違う
などということもあったはず。
どこかに偏るということが今より多くなく、
今より多様性があったのかもしれないな~と。
今使われている言葉は機能的で明確だったり
するけれど、逆に大雑把で何でもかんでも
まるっと一緒にしてしまったりと、
表現については単純になっているのかなと。
何にしても余裕(と学)がなければ、
細やかな表現や暗に意味を示すなどという
言葉遊び的な言葉を使うのもむずかしいもの。
昔のさまざまな表現は雅で美しいけれど、
現代で日常的に使うには少々合わないですよね。
しかしたまにはそんな言葉に触れて、
昔の美意識に浸ってみるのもいいものです。
それでは今回はこのへんで。
ここまでおつきあいくださいまして
ありがとうございます。
梅の言葉を季節とともに感じてみましょう~
ヽ(´ー`)ノ