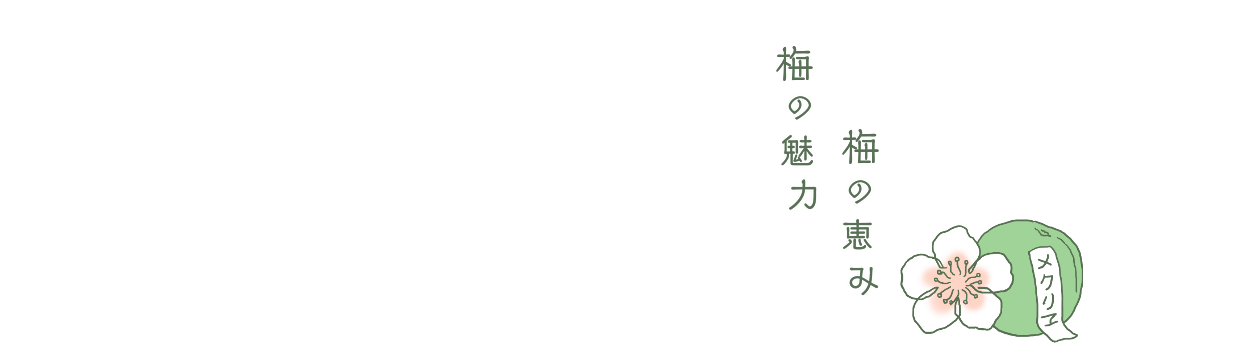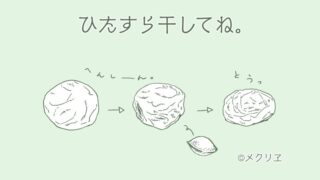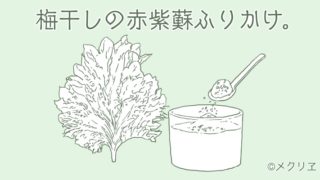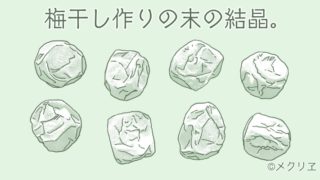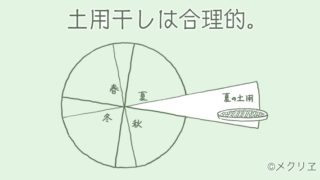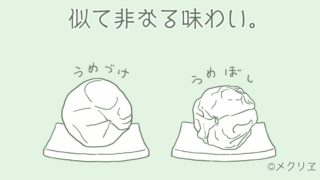梅を干す。
それは梅干し作りの最終工程。
干すから「梅干し」であって、
干さない塩漬け状態のものは
「梅漬け」といいます。
これは干すか干さないかの違いだけ。
梅を「干す」といっても
簡単にできないこともありますよね。
そんなときにはちょっと工夫が必要。
どうしても干せない場合には、
「梅干し」ではなく、
「梅漬け」のままでもいいでしょう。
しかし干すことの意味や性質からいえば、
できれば干した方がお得かなと。
干すかどうかは誰が決めるのではなく、
自分で決めてしまえばいいことなので
気楽に行くとしましょ~!
梅干しを干すということ
梅を干す目的は、簡単に言えば
梅の水分を飛ばすこと。
そして天日によって梅を殺菌すること。
これをすることで
梅干しの保存性を高めます。
昔の人はすごいもので、
太陽光線に殺菌効果があることを
感覚的に知っていたわけです。
いや、厳密には違うのでしょうけれど…
どのみち梅を干すということは、
塩漬けして梅酢に浸かった梅の水分を抜き、
天日に当てて保存性を高めること。
そう思うと、
やはり梅を干すことには意味があり、
やっておいたほうがいいよね~
と思います。
◇ 関連記事記事はこちら。
じつは干さなくても大丈夫
冒頭にも書きましたが、
梅を干すこと自体は簡単なこと。
しかしむずかしいと感じるのは、
その理由の殆どが、自身の環境において
問題があるから…ということでしょう。
住んでいる地域の環境事情や住宅事情、
日照条件、天候、大気、ほかには
干すことに費やす時間的な問題などなど…。
もし梅を干すことをためらわれるの
であれば、干さないという選択肢もある。
梅は必ず干さないといけない、
というものではないので
干したかったら干せばいいし、
干せなければ干さないでもいいのですよ。
ちなみに私は干したいほうなので、
時折干すことを強めにすすめてしまいますが
気にしないで…笑。
干せる時には干す。
干せない時には干さない。
それでよし。
◇ 関連記事
梅を干す時期とタイミング
梅を干す時期には昔から、
「土用」の期間が適している
とされています。
土用の期間に梅を干すのは
意味があってのことなのですが、
その時期を逃してしまって干せない
ということもまた致し方ないこと。
今どきは気候も天候もちぐはぐで、
季節外れの台風が続いたり、
集中豪雨、長雨、梅雨が明けない…
また、どんよりとした天気が長く続いて
結局干せない年もあるものです。
また、たとえ天気のいい日が続いたとしても
その日に用事がないとも限らない。
そんなこんなを繰り返していると、
いよいよ土用の期間は終わってしまいます。
そんなときには、
干せる時に干してしまえばいいのです。
土用の日ではなくとも、
丁度いい天候の頃合いを見計らって
干すのもいいですよ。
◇ 関連記事
梅の干し方
梅の干し方はいろいろあって、
結構自由がきくものかなと思います。
干す場所だったり、干す方法だったり、
あるいは干す道具のことだったり。
自由がきくというよりも、
工夫しないとなかなか干せないという
場合もありますからね~^^;
干せる場所というのはどの家でも
何かしらの限りがあるでしょう。
理想と現実は違うもの。
日照条件なども各家庭で違うので、
干し方も干し場所も
それぞれ違うようになるはずです。
うちも悠々自適に干すことができれば
いいのですが、なかなかそうもいかないので
いろいろと考えます。
家で梅を干すのは厳しいな~と思っても、
工夫次第でなんとかなることもありますよ。
いろいろな情報を集めてヒントを得ながら、
自分なりの干し方を模索してみると
いいでしょう。
◇ 関連記事はこちらへ~。
梅を干す方法と干し具合
初めて梅を干す時、
自分の感覚でいいよ~!
といわれたら困りますよね。
なにしろ初めて梅を干す場合には、
自分の中に基準となるものが
何もないのですから。
そこで基本的な指標として、
三日三晩干しましょう~!
というのがあります。
基本的な方法を自分なりにたどりながら、
その都度、梅の干し具合を観察。
これが一つの自分の基準となっていきます。
そして、このくらい干せたらいいよ~
というマニュアルなどの言葉と、
自分の梅干しのイメージに近くなれば
そこで干すことをやめて保存する。
しかしここで注意なのが、
マニュアル通りにやりすぎないこと!
他の工程はマニュアルどおりで
おおむねいいのですが、
干すことについては、干す環境によって
ずいぶん結果に差が出るもの。
マニュアルを鵜呑みにしすぎないことを
記憶の片隅にでも置いておきましょう。
◇ 関連記事
土用干しの失敗?
梅干しは、梅を塩漬けにした後
干して完成。
その最終作業である「干す」段階において
「失敗した?」ということは
なかなかないのだけれども、
稀に不安になることもあるのですよね。
梅を干していたら白くなったとか
雨が降ってきちゃった…とか。
初めてのことを行うときには
ちょっとしたことでも
心配になったりするもの。
それでも理屈や対処方法がわかれば
安心できたりするのですよね。
そんなときには、
こちらの関連記事をどうぞ。