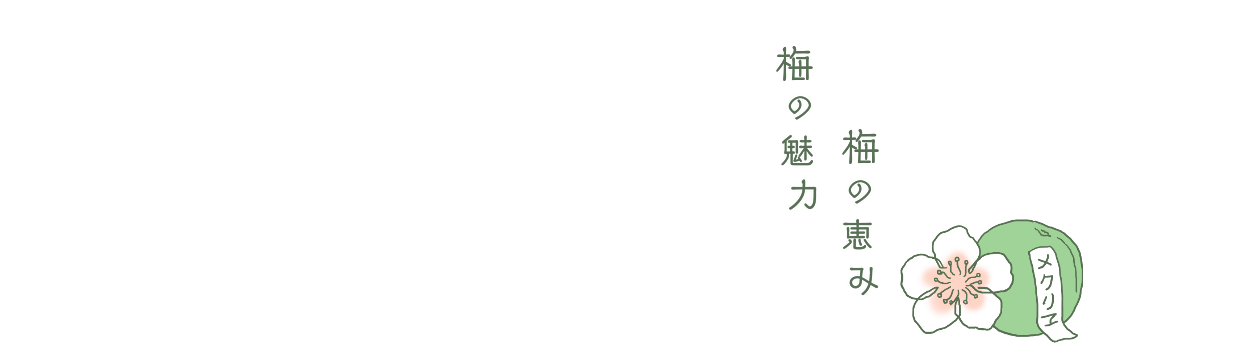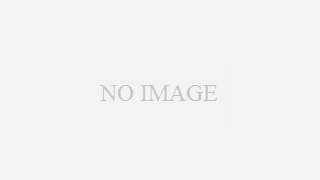梅の花というと、日本人には親しみ深い花のひとつ。
現代では、
春の花といえば「桜」
花見といえば「桜」
そんなイメージが強いのですが、令和の時代になり、再び梅が注目されています。
春の花といえば「梅」
花見といえば、梅!
まぁ、そこまでいかないにしても、梅の花はいいものですよ。
では、梅の花というものを見ていきましょう。
花見といえば梅の花?
花見といえば現代では主に、桜を指します。
しかしその昔、鎌倉時代には桜ではなく、梅でした。
それから平安時代になると、梅から桜へと移行する。
桜のお花見が庶民に広まったのは、江戸時代。
江戸時代は様々な文化が育った時代といわれています。
なかでも庶民が花を愛でる文化は、当時世界的に見ても珍しいものであったようです。
花の品種改良が盛んに行われ、図鑑や園芸書などが出版されていたほど。
梅ももちろん、江戸時代に多くの品種が作られました。
そして現代。
令和の時代になり、あらためて梅がちょっとしたブームになっています。
梅の花は可愛らしく、とても美しいですよ。
全体の華やかさは桜にかなわないかもしれないけれど。
花の香りは、梅の方がわかりやすく芳しいものです。
梅というもの
梅はそもそも中国から渡ってきたものとされていますが…
日本に自生していた説などもあり、様々な見解があります。
梅は日本の風土に合い、古くから日本人に好まれ愛されてきました。
そして文化的にも根付いており、品種も多く作られています。
梅の生息域
梅は日本や中国、台湾などの気候に合うもの。
そのほかの環境では、なかなか梅は育ちにくい。
そのため他地域の諸外国では、あまり梅というものに馴染みがないようです。
梅を翻訳ツールで英語にしてみると「plum(プラム)」と出てくる。
plumは、プラムやスモモを表し、梅とは違う植物。
(ちなみにプラムとスモモは同じもの)
果実の違いを見れば、一目瞭然に違うものだとわかります。
梅がプラムと訳されるということは、少なくとも、梅は英語圏にはないようです。
海外の梅といえば
海外の梅といえば、浮世絵の梅を模写した、ゴッホが思い浮かびます。
梅は江戸時代の浮世絵に多く描かれ、画家であるゴッホが、広重の梅を模写したことで有名です。
厳密に言えば、梅の花だから模写したわけでなく、広重の手による構図の取り方や描き方、色彩などに衝撃を受けたから模写したのでしょう。
- 関連記事
ゴッホは広重の梅を模写した
浮世絵はヨーロッパで流行ったジャポニズム(日本趣味)とともに、多くが海外に渡りコレクターによって集められました。
当時としては物珍しい日本の製品は、その感覚の違いからとても斬新に見えたことでしょう。
- 関連記事
浮世絵での梅の役割
梅に似た花
梅に似た花は数々あります。
そして梅の字を冠した花も多くある。
そのなかで、春に咲く花は特に間違いやすいものです。
ロウバイ
ロウバイという植物があります。
ロウバイは漢字で、蝋(ろう)のような梅で「蝋梅」と書く。
形が梅に似ていて、花咲く時期も近い。
というより、開花時期は梅よりロウバイのほうが幾分早い。
梅は百花の魁(ひゃっかのさきがけ)という言葉があります。
しかし梅より、ロウバイのほうが咲くのは早いのです。
そしてロウバイは、梅に似ているけれど梅ではないのですよ。
ここはちょいと引っかかりますね。
梅がロウバイより人々に身近であったのか、ロウバイも梅だと認識されていたのか…。
調べてみると、ロウバイは江戸時代の頃に中国から入ったもの。
梅は奈良時代には既にあり、共に過ごした歴史が違う。
つまりはそういうことでしょうか。
- 関連記事
梅とロウバイは他人だよ
梅と杏、桃とアーモンド
次に似た花として、杏があります。
杏は梅と仲間であり、分類も同じバラ科のサクラ属(あるいはスモモ属)。
梅と交配しやすく、品種の見分けは難しいとされる。
杏は梅より花が大きく、花数も一節に2~5個と梅より多い。
そして開花期は梅よりおそく、果実は酸が少なく黄熟する。
- 関連記事
梅と杏の違いとは
次に、桃。
桃も梅に似ていて、開花時期も近い。
しかし梅と桃とは、各部位に違いが見られるため見分けがつきやすいのです。
そして桃の仲間である、アーモンドの花も梅と似ている。
アーモンドの分類は、桃と同様のバラ科サクラ属(あるいはモモ属)。
梅とも雰囲気は似ています。
ゴッホが贈り物として描いた絵に、アーモンドの木がある。
このアーモンドの木の絵は、浮世絵へのオマージュが感じられるもの。
日本の梅と似ているから描いたのかは定かではないけれど、ヨーロッパに梅はなかったのでしょうね。
桜
春の花は梅から始まり、桃、桜と開花していく。
(品種によってはズレがあるので、そのあたりは割愛しますよ~)
梅と桜の見分け方は、とてもわかりやすい。
花の付き方が違うし、花びらの形なども違います。
また、花がなくとも木の幹で区別がつきやすいのは、桜。
桜の幹には横縞があるので、とてもわかりやすいのです。
対して梅の幹に横縞はなく、幹肌がゴツゴツとしています。
- 関連記事
梅・桃・桜の見分け方
梅がシンボル
都道府県のシンボルとして、それぞれ木・花・鳥などがありますよね。
このシンボルとして梅を掲げている自治体があります。
◇ 都道府県の木
シンボルの木として、県木に梅の木を指定している県。
- 茨城県
- 大分県(豊後梅)
◇ 都道府県の花
シンボルの花として、梅の花を指定している府県。
- 大阪府
- 和歌山県
- 福岡県
- 大分県(豊後梅)
大分県にいたっては、県木・県花として豊後梅を指定しています。
これは大分県が豊後梅の産地であることから、梅ではなく、豊後梅を選定されたようです。
さらに市町村でも、シンボルとして市町村の木・花・鳥があります。
そこにはもちろん、梅を指定している市町村があります。
これまはた別の記事にて、書…けたら書くかもです。
あらゆるところに梅の花
梅の花は、日本人に昔から親しまれています。
その証拠?に、梅の花を題材としたいろいろなものが作られていますよね。
歌や曲、印章やロゴ、ハンドメイドなどのものづくり。
あらゆるところに梅がモチーフとして使われています。
梅の花の形を模した組紐、折り紙、クラフトなど以外にも、梅の花のいい香りなど、梅の花はいたるところで楽しまれています。
- 関連記事
・うめぼしのうた
・梅は咲いたか、桜はまだかいな
・梅の花の香り
「花といえば梅」という奈良時代から現代に至るまで、私たちには自然に刷り込まれてきた何かがあるのかも知れないですね。
寒さという苦難に耐え忍んだ先に花ひらく、梅。
一斉に咲き誇り、はらはらと舞い散る儚い桜。
あなたはどちらがお好みでしょう。
まぁしかし、どちらかを選ぶ必要もなく。
春先にはぜひ、梅から始まる花々の開花に注目してみてくださいませ。
なお、梅の花のアレルギーなどもあるみたい。
花粉症などにお心当たりのある方は、お気をつけて。
それでは今回はこのへんで。
ここまでお付き合いくださいましてありがとうございます。
いろいろな梅の花をご堪能あれ~ヽ(´ー`)ノ