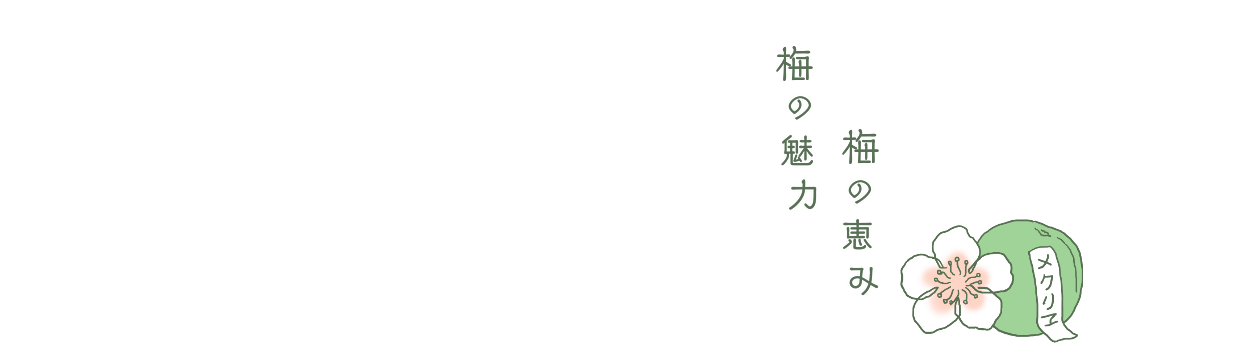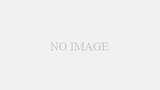この記事を読むのに必要な時間は約 10 分です。
梅はとても種類の多い植物。
それには梅の特性が絡んでいます。
素人目にはなかなか区別が付きにくいといわれているのですが、
それは梅の特性によって種類がとても多いことと関係があるのでしょう。
その特性とは。
梅の花にはどんなものがあって、どんな違いがあるのか。
そんな私も素人なので、調べながらわかりやすい部分を取り上げていきます。
梅の花にはこれだけの違いがあるということを知るだけでも、また違った見方で梅の花を楽しめることでしょう。
それでは一つずついってみましょ~。
梅の花の種類
冒頭にも書きましたが、梅はとても種類が多いもの。
日本国内だけで400品種以上あると言われています。
梅の種類についての分類はいろいろな見方があったようで…
さまざまな分類説がありすぎて、調べれば調べるほど混乱しました^^;
ここでは一般的によく使われている分類について紹介していきます。
花梅と実梅
梅は大きく分けて「花梅」と「実梅」とに分けられます。
これは用途での分類。
- 花梅
花が美しく、観賞用として愛でられるもの。
花の形や色だけでなく、香りや幹の形・枝ぶりなど全体も鑑賞対象。
- 実梅
果実がよく成り、大きく質の良いもの。
実の品質は元より、育ちやすさやなども追求されている。
花梅と実梅。
分けられているからには、きっちり分類されるのかと思いきや、じつはそうではなく。
花梅と呼ばれるものでも実は成るし、質のよいものもある。
実梅と呼ばれるものでも、花が美しく香りのよいものもあるのです。
花梅と呼ばれるものの定義は特に固まっていないようなのですが、
その数は300種以上はあるのではといわれています。
実梅と呼ばれるものは100種以上はあるということ。
梅のすべての品種が登録されているわけではないので、全容は不明。
梅の特性から種類が増えやすい植物で、雑種も多く、品種が特定できないものも少なくないようです。
花梅の分類
花梅の分類について、一般的に次のようなものがあります。
主に花梅の分類と言われているのですが、実梅にも当てはめるようです。
- 3系9性(あるいは8性)
分類を3つの系と、8または9つの性(しょう)とに分けるというもの。
- 野梅系(やばいけい)
… 野梅性・紅筆性・難波性・青軸性
梅の原種に近い種。枝が細い。花や葉も小さめ。 - 緋梅系(ひばいけい)
… 紅梅性・緋梅性・(唐梅性)
枝の髄が赤く表面は黒っぽい。花は紅色、まれに白色。 - 豊後系(ぶんごけい)
… 豊後性・杏性
枝が赤っぽく、節くれだっている。開花が遅い。
「性」での分類は難しいとされるが、参考までに少し説明を書いておきます。
野梅系(やばいけい)
- 野梅性(やばいしょう)
原種に近い。枝は細く若枝は緑色、日焼けで赤み。葉は小さめで毛がない。
品種:道知辺・冬至・八重寒紅・思いのまま・見驚・鶯宿・臥龍梅・玉英など - 紅筆性(べにふでしょう)
紅い蕾の先が筆のようにとがっている。
品種:紅筆・内裏など - 難波性(なにわしょう)
枝が細く茂り、葉は丸い。
品種:難波紅・蓬莱など - 青軸性(あおじくしょう)
若枝と萼が黄緑色。花は青白い。
品種:緑萼・月影・白玉など
緋梅系(ひばいけい)
- 紅梅性(こうばいしょう)
花明かるい紅色。若枝の色は濃すぎず緑色っぽい。
品種:鴛鴦(えんおう)・大盃・東雲・緋の司・紅千鳥など - 緋梅性(ひばいしょう)
花の紅色が濃いもの。樹勢が弱い。
品種:緋梅・鹿児島紅など - 唐梅性(とうばいしょう)
下向きに咲き、咲き終わりは色が抜けぎみになる。
品種:唐梅
豊後系(ぶんごけい)
- 豊後性(ぶんごしょう)
杏との雑種性が強い。枝は太め。花は淡く紅色が多い。
品種:楊貴妃・八重揚羽・藤牡丹など - 杏性(あんずしょう)
豊後性より枝が細い。葉は小さく表面に毛がない。
品種:緋の袴・一の谷など
咲く時期の違い
早咲き・中咲き・遅咲き
というのを見聞きしたことがあるでしょう。
開花時期は、早咲き・中間・遅咲きとはっきり別れるものでなく、少し早いとか、少し遅いものなどいろいろです。
- 早咲きといわれる梅
冬至・道知辺・八重寒紅・鹿児島紅・千鳥・大盃
竜峡小梅・花香実・養老・小梅など。 - 遅咲きといわれる梅
見驚・月影・黒梅・武蔵野・摩耶紅梅・未開紅・黒田
白加賀・南高・豊後など
梅の開花時期は一般的に1月下旬から3月下旬頃にかけてですが、この間に様々な品種が咲いては散るのです。
(場所によっては4月~5月ということもあり)
また、早咲きの部類は気温によって開花時期の変動が大きく、遅咲きでは変動が少ないといいます。
梅の特性
純粋なウメは早咲きが多い、という話があります。
そして遅咲きの梅は、梅と杏とが交じった豊後系(杏系)の梅が多い。
これは開花時期が杏と同じ頃だからです。
梅と杏は種が近い。
梅は、自分や同種の花粉では受粉しないものも多いのです。
そこで開花の時期が重なる別種と交配し、雑種ができる。
(どれでもいいわけでなく、合う・合わないはある)
早咲きの梅は、ほぼ梅しか咲いていない時期。
そこで別品種の梅と交配するのです。
遅咲きの梅は、ちょうど種の近い杏の時期と重なります。
そこで別品種の梅だけではなく、杏が交じる。
これが梅の特性。
品種が多いのもうなずけます。
梅は種類が多いので、有名なもの以外にも多くの品種があります。
そして品種不明の名もなき梅も、沢山あるようです。
梅の花のいろいろな違い
梅の花の形や色は多岐にわたる。
たくさんある種類をじっくりと見てみると、いろいろな違いがあることがわかります。
花の形
花びらの形は同じように見えるものも沢山あります。
しかしよ~く見てみると、少しずつ違うことも。
花の正面から見て
〔花びらが丸い形〕
- 付け根が丸い
- 付け根が細い
- 付け根が更に細くくびれて、隣との間に隙間がある
〔花びらが尖った形」
- 先が尖っている
〔花びらが縮れた形〕
- 縮れたようになっているもの
- ひらひらとした形のもの
〔花びらが退化した?〕
- 花びらが細いもの
- 花びらが殆どないもの
花の横から見て
〔花の横からの形〕
- 花が丸くお椀型のもの
- 花が平べったい状態のもの
- 花びらの先がひるがえっているもの
雄しべと雌しべ
〔雄しべと雌しべの違い〕
- 雌しべが一本
- 雌しべが多い
- 雄しべや雌しべが長い
花の色と模様
梅の花びらの色は、白や薄い紅、濃い紅など。
また、一色ではなく柄のように色が入るものもあります。
梅の花は元々白いもので、そこに杏が交じることで紅色が入ったという説もあります。
特に実梅は多くの花が白く、薄い紅色やピンク色もあるが、濃い紅色の品種はないようです。
〔花の色〕
- 白色
雪のような白色、青白い色など - 淡い色
淡い黄色や淡い紅色など - 黄色
柔らかな黄色や白っぽい黄色など - 紅色
桃色やピンク色、濃い紅色など
〔模様〕
- 花びらの付け根に色が入るもの
- 色つき花びらの縁が白く抜けたもの
- 白い花の1枚から数枚に色がついたもの
- 花びらの一部に筋が入ったもの
などなど。
一重と八重
梅の花には一重と八重咲きがある。
一重の花は、花びらが5枚が基本。
八重といわれるものはだいたい15枚。
もっと多い花びらの数を持つ品種も在る。
また、花びらの多い品種には、雌しべを2本以上持つものもあるようです。
この場合、一つの花に複数の実がなる場合がよくあります。
「夫婦梅」や「八房の梅」と呼ばれるのも、この類のもの。
一つの花をじっくりと観察してみるのもいいでしょう。
後記
今回は梅の花の種類について調べ、書いてみました。
品種がとても多いので、一つずつ紹介したくもありましたが、なにせ多い。
なのでここでは、品種の違いについての紹介に留めました。
梅の花は多種多様。
色もさまざま。
形もさまざま。
咲く期間もさまざま。
梅の花は徐々に開花して満開になり、散るまでの期間が長い。
複数の品種が植えられている場所なら、行く時期をずらして再度訪れると、また違った景色が楽しめるでしょう。
沢山植えてある場所では、遠目からの景色を。
少数が植えてある場所では、ひとつひとつの花を。
じっくり鑑賞してみるのも、なかなかいいものです。
それでは今回はこのへんで。
梅が咲けば春はすぐそこ。
今年もいい春がやってきますようにヽ(´ー`)ノ