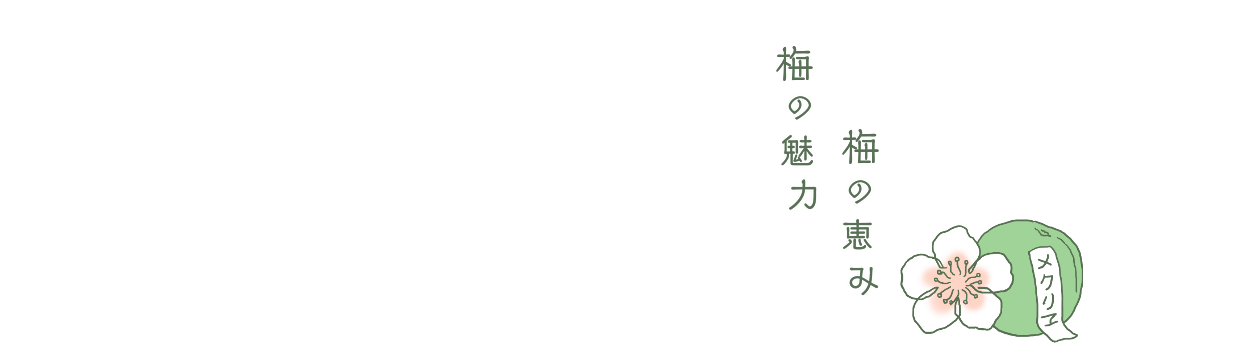この記事を読むのに必要な時間は約 22 分です。

梅の実が出回る時期。
スーパーなどで梅が並んでいると、
「今年こそは!」と、いきなり衝動買いをしてしまうこともあるでしょう。
梅干し、梅漬け、梅酒に梅シロップ…作れるものはいろいろ。
梅を買ってしまってから「どうしたらいいんだっけ…?」と悩んだり慌ててしまわないよう。
何を作りたいのかを決めて、必要なものを確認しておきましょう。
道具もそのひとつ。
梅を加工するための道具は、何が必要で何を使ってはいけないのか。
事前に知っておくと安心です。
- 作業を始めてから慌てない
- 道具を買いに行ってから悩まない
- 知らずに失敗することを防ぐ
道具はいきなり全て揃える必要はなく、家にあるもので代用できるものはそれを使えばいいのです。
梅でなにを作るにしても、だいたい同じ道具が使えます。
このページでは、一番工程が多い梅干し作りの工程を例に挙げながら、使う道具や代用できる道具について説明していきます。
梅を加工する前に使う道具たち
梅干しに限らず、他の梅の加工や保存食を作るときにはまず、やることがあります。
それは、道具を洗って消毒するということ。
道具に付いているゴミやホコリ、雑菌などを取り除くために必ず行います。
道具を洗う作業は、食器を洗うのと同様。
消毒には、熱による消毒と消毒液などを使う方法とがあります。
熱による消毒をする場合
熱による消毒には2つの方法があります。
【熱による消毒】
- 煮沸(しゃふつ)消毒
道具が入る大きさの鍋が必要 - 熱湯(ねっとう)消毒
鍋やヤカンなど、湯が沸かせる道具が必要
aの煮沸消毒では、道具を鍋の中の湯で煮ることになるので、その道具が入る大きさの鍋が必要になります。
大きな鍋がない場合には、bの熱湯消毒をします。
bの熱湯消毒の場合には、湯を沸かすことができればいいので、片手鍋でもヤカンでも、家にあるものを使えばいいです。
熱に弱い道具を使う場合にはもちろん実施できないので、別の方法で消毒します。
- 熱による消毒の詳しくは、次の記事をどうぞ。
→ 容器の消毒の方法とその理由
→ 煮沸・熱湯消毒の方法~瓶(ビン)について
消毒液などを使う消毒の場合
消毒液として使えるものにはいろいろな種類があります。
大きく分けると次の2種類。
【消毒液などを使う消毒】
- 度数35%以上のアルコール
・35度以上の焼酎(ホワイトリカー)
・ブランデーやウォッカなど強いお酒
アルコール度数の高いお酒ならばよし。 - 食品に使える消毒液など
・ドーバー パストリーゼ77 など
・食品に使ってもよいとされる消毒液
どれでもいいので、1種類はあると便利。
強いお酒が家にあればそれで代用できます。
- アルコールやその他の消毒について
→ アルコールや酢などでの消毒
道具の消毒について
基本は熱による煮沸消毒や熱湯消毒がいいでしょう。
しかし熱に弱い道具にはできないので、35度以上のアルコールや消毒液を使います。
なお、いちばん良いのは二重に実施すること。
- あらかじめ熱による消毒をして乾かしておく
- 梅を漬ける直前にアルコールや消毒液を用いて消毒する
これはカビを出して腐らせたりする雑菌を排除するため、失敗をしないためにも大切な工程のひとつなのです。
梅を下処理するときに使う道具たち
梅干しを作るとき、梅を加工する際には、まず梅の重さを量り、材料を量ります。
それから梅を洗い、水を切って乾かし、梅のヘタを取るなどして漬け込みます。
それらの工程で使う道具を説明します。
梅などの重さを量る道具
【計量器】
- アナログ式のはかり(ばねはかり)
- デジタル式のはかり(電子はかり)
重さがわかればどちらでも。
キッチンスケール、クッキングスケールとか呼ばれているもので充分。
重さがわかればいいのでお好みで。
ウチでは2kgまで量れるものを使っています。
梅や塩以外の材料を使って漬けたいときには、計量カップや計量スプーンなども必要になりますね。
これらは家にあるもので十分です。
梅を洗って水に浸けておく道具
- 桶(おけ)やボウルなど
梅を水洗いできて、アク抜きのために水に浸けておくことができる道具。
桶やボウルがなければ、洗面器や大きめの鍋でもいい。
代用できる大きめの入れ物があればいいでしょう。
材質については、琺瑯(ほうろう)製、ガラス製、陶器製、プラスチック製など何でもいい。
梅は金気を嫌いますが、一時的な作業の場合は、ステンレス製のボウルなどでも大丈夫です。
梅を乾かす道具
- 風通しのよいザルやカゴなど
竹製品、プラスチック製品など。
網目の粗いものが乾きやすくてよいです。
ザルは梅干しを干すときにも使えるので、あればなにかと便利。
金属製の網の場合、梅をそのまま乾かす程度なら大丈夫かと思いますが、長い間置きっぱなしにしたり、梅を切って干すなどの使用は避けたほうがいいでしょう。
梅のヘタを取る道具
- 竹串、爪楊枝など
爪楊枝よりも、竹串のほうが先が潰れにくいので使いやすい。
梅のヘタを取るかどうかは好み。
どちらでもいいのですが、手間を惜しまないなら取るほうがオススメです。
ヘタを残して漬けると苦味が出るという話を聞きますし、食べるときにも口に残るしね。
また、ヘタを取る以外に、梅の実に穴を開けるとき(※)にも使います。
※梅シロップを作るときなど。
梅の水気を拭き取る道具
- 清潔な布巾(ふきん)、キッチンペーパーなど
梅を漬けるときには基本的に水気厳禁。
梅を自然乾燥するか、水気を拭き取るものが必要です。
梅を漬けるための道具たち
梅干しなど、梅を加工するときには、どの容器を使って梅を漬けるのか、事前に決めて用意しておきます。
梅を漬けておく容器
【梅を漬けておくための容器】
- 果実酒用の瓶(ビン)
- 漬物容器(琺瑯・陶器・プラスチック製等)
- 漬物用ビニール袋
- ジッパー付きビニール袋
※注意事項※
梅を漬ける期間は約ひと月前後、またはそれ以上の長期間に渡ります。
金属製の容器は腐食する恐れがあるので、絶対に使わないこと。
梅干しを漬けるための容器は種類も多く、大きさもさまざま。
どれを使えばいいのかは漬けたい梅の量にもよるし好みによります。
どの容器を選択するかで、漬け方や注意点などが少々変わってきます。
使いたい容器での梅干しの作り方をあらかじめ調べておくといいでしょう。
初心者さんなら、手間がかからず失敗の少ないビニール袋で漬けるのがおすすめ。
梅が500g~1kgの少量ならジッパー付きビニール袋。
一度に多く漬けるなら漬物用ビニール袋。
漬物用ビニール袋は大きいので、これを入れる容器が必要です。
初めて漬けるからあまりお金をかけたくない…
そんなときには、容器も代用品でまかなえます。
【漬物用ビニール袋を使うときの容器の代用品】
- 段ボール箱
梅の容量に合う大きさのもの - ポリバケツ
梅の容量に合う大きさのもの
うちでも漬物用の容器が足りないときに使ったことがあります。
ダンボール箱で梅干し10kg…これはちょっと多すぎてしんどかった。
ポリバケツで5kg…非力なのでこのくらいが丁度いい。
実際、ビニール袋を支えるだけの外側なので、容れ物なら何でもOK。
それでも、金属の容れ物は避けたほうがいいかもです。
それと、漬物用ビニール袋無しでポリバケツに直に梅を漬けるのはやめましょう。
食品用(漬物用)の容れ物でないと、梅は酸が強いために何が溶け出すかわからないからです。
これはポリバケツのみならず、陶器(かめ)やビンについても同様。
あまりに安い品は直漬けに使わないのが無難です。
容器選びの詳細については、関連記事をどうぞ。
→ 梅の容器はどれがいい?
→ 梅の容器の大きさは?
落し蓋と重石
使う容器によって、ほかに必要な道具というものがあります。
- 落し蓋(おとしぶた)
- 重石(おもし)
※ 注意事項 ※
金属製の落し蓋や重石は絶対にダメ。
木製であっても、金属の金具が使われているものがあるので気をつけましょう。
果実酒用の瓶(ビン)の場合
果実酒用のビンは、落し蓋も重石も使わずに漬けるのが一般的。
瓶の口が狭いものが多いので、落し蓋や重石を入れるのに向かないのです。
しかし重石を使うほうが、早く梅酢が出て安心できるのも事実。
重石を代用するなら、ビニール袋を二重にして、小さめの石などをきれいに洗って乾かし入れます。
子供のビー玉やおはじきなどが大量にあれば、それらをきれいに洗って乾かし、詰めてもいいでしょう。
重石に水を入れたビニール袋を使うという方法がありますが、これはおすすめできません。
ビニールから水が染み出したり、水が漏れたときに気づくのが遅れてしまうと、梅が傷んでしまいかねないからです。
まだビンを持っていないけれど是非ビンで漬けたい!という場合には、近年は落し蓋と重石がセットになった広口の瓶が販売されているので、こちらもおすすめです。
漬物容器(琺瑯・陶器・プラスチック製等)の場合
漬物容器を使う場合は、落し蓋と重石は必須。
専用の道具としてホームセンターなどで販売されていますが、結構ゴツいし邪魔になるので…
うちではいつも代用品で賄っています。
【落し蓋の代用】
- 容器の大きさに合うお皿
漬物容器に漬物用ビニール袋を入れて梅を漬ける場合には、ビニール袋を閉じた上に置きます。
漬物用ビニール袋を使わず、直接落し蓋を入れる場合には、熱湯消毒をして乾かしてから入れましょう。
ちなみに家では前者で行っています。
ビニール袋の上からのほうが梅酢に濡れなくていいし衛生的です。
【重石の代用】
- 塩袋や砂糖袋
1kg毎にそのまま乗せられるので便利 - ペットポトル
500ml、1L、2Lなど、そのままの重さで調整できるので便利 - 分厚い本や辞書
塩袋やペットボトルがないときに。(重さがわからん)
どれも一応、ビニール袋に入れてから乗せるほうが無難です。
漬物用ビニール袋から梅酢が溢れたとき、ベタベタになるからねぇ…(経験済み)
ジッパー付きビニール袋の場合
ジッパー付きのビニール袋の場合、トレーの上に梅を漬けたビニール袋を寝かせて、ビニールの口を折り返しておきます。
【落し蓋の代用】
- トレー(トレイ)
スーパーなどで買い物をしたときの白トレーとか。
通常は洗って回収所に持っていきますが、梅の時期はこれを置いておいて使います。
落し蓋の代用品として平らな皿でもいいですが、ジッパー付きのビニール袋が四角いので、このトレーが大きさも形も丁度いいのですよね。
【重石の代用】
- 塩袋や砂糖袋
先程と同様、重さがあって上に乗れば何でもいいのですが、塩袋が大きさも丁度よくて使いやすい。
梅の時期は塩や砂糖、氷砂糖を結構使うので、まとめて買っていたりしますからね。
梅を干すときに使う道具
梅干し作りの終盤。
梅を塩漬けにして1ヶ月くらい経てば、いよいよ梅を天日に干して仕上げです。
【梅を干すときに使う道具】
- ザルやカゴ
- 干し網
- 梅布
竹製品で底が平らなものがおすすめ。
干す専用のプラスチック製品もあります。
梅布は平らなところに敷いて使う布。
梅をまとめて取り込めるので、あると便利です。
【梅を干すときに使える代用品】
- 巻きす
少量ならこれでもいける - すだれ
結構な量が干せる
風通しのよい網目状の道具なら何でも使えます。
ただ、代用品を使う場合にはちょっと注意。
巻きすはそもそも食品用なのでいいとして。
すだれの場合は防カビ加工が施されているものもあり、食品に直接使うのはどうかな?とも思うので、その場合には梅布などを広げた上に干すのがいいかもです。
そして、 金属製品は要注意!
短時間なら大丈夫かも?とか思うけど、2日あるいはそれ以上の期間干しっぱなしにすることもあるし、夏場は高温になったりとか…心配になるので、少なくとも私は使わないです。
干すための道具は、干す時期までに用意すればいいのですが…
ホームセンターなどの量販店では、季節物の商品を先行して売るので、早い時期から出回ることが多です。
ちょうど梅を干す土用の時期(7月下旬~)には、すでに売り切れているなんてこともあるので、用意はお早めに。
竹製のザルは野菜を干したりなど他にも使えるので、あるとそれなりに便利ですよ。
完成した梅干しを入れておく道具
梅が干し上がれば、保存容器に梅干しを保管します。
梅干しを入れておく容器
梅干しは塩分濃度や保存方法にもよりますが、長期間の保存が可能。
そのため、長期間保存をする前提で保存容器を選びます。
【梅干しを入れておく容器】
- 食品用の密閉できる容器
長い間、梅干しを保存するのに使う容器は、劣化したりニオイ移りのしない素材のものがいいでしょう。
短期間であっても、色や匂いが付きにくい瓶(ビン)や陶器が好ましいです。
おすすめは、瓶で密閉できる容器。
ですが減塩で作った梅干しなど、数ヶ月間で食べきってしまう前提ならば、食品用のビニール袋やプラスチック容器でもいいでしょう。
どちらにしても保存容器はあらかじめ消毒するので、前述の消毒道具はここでも使います。
※ 金属製品はダメ ※
金属製の容器はもちろんのこと、蓋が金属製というのもよくないです。
容器は瓶でも蓋(ふた)が金属というものがよくありますが、金属製の蓋は錆びます。
金属製の蓋しかない場合、うちではラップをした上から金属の蓋をしています。
ラップが破れたり隙間があると、やはり蓋は錆びます。
直接梅に触れていなくても錆びるのです。
うちでは金属製の蓋がダメになった場合、ラップして瓶の口にゴムをかけ、その上から密着するシリコン蓋をかぶせて使っています。
ラップも空気を通したりするので、これでいいのかどうかは…厳密には謎ですが。
まぁ、家で食べるものなので、どうするかは自己責任ですよ~。
梅酢の処理に使う道具
塩漬けした梅を干したあとに残った梅酢。
これについては、処理の方法はいろいろあります。
- そのままで別の容器に移して保存
- 天日に晒して干し、冷まして保存
- 火にかけて冷まして保存
どのように処理するかは好みでいいのですが、火にかける場合に注意。
梅の酸や塩分に強い鍋を使うようにしましょう。
【梅酢を火にかける場合の道具】
- 琺瑯(ほうろう)
- ステンレス製の鍋
- 土鍋など
金属製品は基本的に不可ですが、ステンレス製の鍋は可。
ただしステンレス製の鍋であっても、梅や梅酢を入れたまま数日間放置するようなことは避けます。
使い終わったら、すぐにきれいに洗ってしまいましょう。
保存容器に移すときの道具
梅干しなど、加工したものを保存容器に移してしまえば、いよいよ梅仕事の完了です。
【梅干しなどをつまむ道具】
- 菜箸
梅を保存容器に移すときなどに使います。
素手を使う場合もありますが…これは人それぞれ。
【梅酢などの液体を移す道具】
- 木杓子、おたま(レードル)など
- 漏斗(じょうご)
梅酢などを保存容器に移すときに使います。
おたまやレードルは一時的に使うものなので、ステンレス製でも可。
使い終わったらすぐに洗います。
漏斗はプラスチック製が軽くて使いやすい。
梅酢は料理などいろいろと便利に使えるので、丁度いいサイズの細口の瓶などに移して保管しておくと便利です。
その他の特殊な道具(必要なら)
特殊な道具は、余裕があれば持っていてもいいでしょう。
ただ、あまり使わないなら、いらないかな~。
梅を特殊な漬け方をするときに使います。
たとえば、梅の実を割るとか、種を抜くとか。
そんなときに使う特殊な道具も一応紹介しておきます。
梅の実を割る道具
- 梅割り器
ネットで検索すると沢山出てきます。
滅多に使わないのに買うのもねぇ…
という場合の代用の方法は次のようなもの。
- 梅の実に包丁で縦に切れめを入れる
- まな板と木ベラ(木片など)で梅を挟み
- 金槌で叩く
この手順で梅が割れるようですが…
私は力が及ばず?再現できなかったです^^;
必要ならあったほうが楽かも。
種を抜く道具
- 種抜き器
これもネット検索すると出てきます。
代わりの方法としては、包丁やスプーンで地道にえぐる…。
やったことがありますが、これ、数やるのはけっこうしんどいです^^;
包丁もスプーンも金属ですので、作業が終わったらすぐにきれいに洗ってしまいましょう。
※注意事項※梅に使ってはいけない道具
梅に使う道具は、ただただ、金物や金属製品に注意!
度々しつこいようですが…
梅の作業全般を通して、基本的に梅と金属は合いません。
梅の酸によって金属が腐食してしまうから。
また、梅干しを漬ける際には、大量の塩も使うのでなおさら金属NGです。
梅に直接触れていなくても、意外と錆びていってしまいます。
うっかりそのまま置いておくとどうなるか…
何より、せっかくの梅ちゃんが、金気臭くなるわ金属が溶け込むわ…なんてことになれば廃棄するしかなくなります。
悲しくなることは避けましょう~(;_;)
まとめ
梅干しなど梅を加工するときに使う道具。
ひとつひとつ紹介していくと結構たくさんあるものですね。
しかしなんだかんだ言っても、漬ける容器と乾かすザルさえあれば、あとは家にあるものでなんとかできそう。
基本はこれら3つの道具があればいい!
- 梅を漬ける容器
食品用の容器で金属製ではないもの
空になった大きな海苔瓶でもよし。
食品用のビニール袋なら安くかさばらない。
- 消毒用のアルコール(度数35%以上)
梅を漬けるには道具の消毒が大切
塩分20%以上で漬ける梅干しなら、熱湯による消毒だけでも充分ですが、あると便利。
- 梅を乾かし干すための道具
ザルやカゴなど
通気性のよい道具があれば代用できる。
いっそ干さない梅漬け状態でよければ、干すための道具はいらない。
(でも梅干しはやはり干したほうがおいしいよ…?)
保存容器は何か食品が入っていた空き瓶でもいいし、家にある保存食器でもいいでしょう。
家にあるもので使えそうなものは、なんでも代用しちゃいましょう。
毎年続けて梅を漬けるのならともかく、初めての場合は専用のものを揃える必要も
ないのです。
道具を選び使う上で気にしておくことは、金物注意!これだけは覚えておきましょう。
それでは長くなりましたが
今回はこのへんで。
ここまでお付き合いくださって
ありがとうございます^^
あなたのところに来た梅ちゃん、
ぜひ大事に漬けてあげましょ~ヽ(´ロ`)ノ~