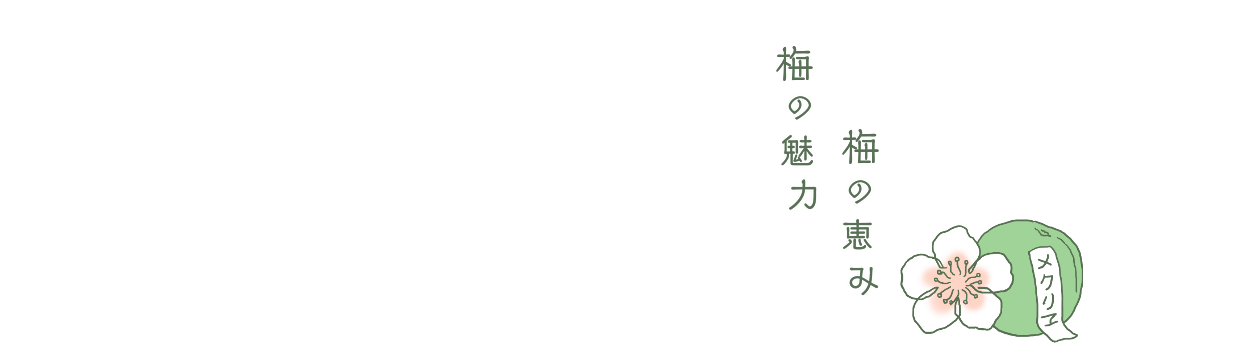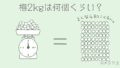この記事を読むのに必要な時間は約 16 分です。

梅を漬けてみようと思うとき、
どのサイズを選べばいいのかな~と
いうことがありますよね。
大きいサイズ、小さいサイズ。
基本的には好みでいいのですけど、
初めて梅を漬けるときには、
作りやすさという点で
それなりに適した大きさを使うほうが
無難だということがあります。
梅のサイズはS~4Lくらいと幅広く、
規格外の大きなものもある。
極端なものを選んでしまうと、
うまくいかなくて失敗してしまう
ということもありますからね。
梅干し、梅シロップ、梅酒、梅サワー…
どれも作るのは難しくないものの、
梅のサイズで左右されることも
実際にあります。
小さい梅・大きい梅の
扱いやすさ、扱いにくさ。
漬ける工程での浸かりやすさ、
浸かりにくさ。
今回は、梅のサイズによって何がどのように
影響するのか、ということについて
書いていくことにします。
梅のサイズを選ぶ基準は
冒頭でも書きましたけど、
梅のサイズを選ぶ基準というのは
とくに決まったものなどはないので、
基本的には自由です。
どんなサイズを選んでもいいのですが、
このくらいのサイズが漬けやすいよ~
という推奨みたいなものはあります。
それは作りやすさにおいてですね。
基本的には、あまり小さいものよりは
少々大きめサイズのほうが漬けやすく、
初めて梅を漬ける場合にはとくに、
Lか2L、あるいは3Lくらいまでのサイズが
手頃で使いやすいかと思います。
何を作るのかにもよりますけどね。
それ以上の大きすぎる梅の場合は、
逆に漬けにくいこともあるのです。
細かいことは後ほど述べていきますが、
まずはそれだけ知っておくといいでしょう。
そしてあるていど梅の加工に慣れれば、
好みで自由にサイズを選べばよし。
たとえばこんなこと。
・梅の果肉を食べるから大きい方がいいな
・気軽に食べたいから小さい方がいいな
・食べやすいから中くらいがいいな
・エキスを抽出したいから大きいのがいいな
…などなど。
好みで選べばそんな感じで決めますよね。
自分の好みプラス、漬けやすさなどの
情報を取り入れるなどして、自分なりの
サイズ選びの基準を作っていきましょう。
梅の漬け方による適したサイズ
梅で何を作るのかによって
材料や漬け方などは異なりますが、
どれを作るにしても
「梅の果汁(梅酢)を抽出する」
という点においては変わりはないのですよ。
梅酢は少ないより多いほうがいい。
そのため、小さいサイズの梅よりも
梅酢を多く含有している大きめサイズの
梅のほうがいいのです。
梅を漬けるには大きく分けて
2つのパターンがあります。
(イ) 塩や砂糖など粒状のもので梅を漬ける
・梅干し、梅シロップなど
(ロ) 焼酎や酢など液体を入れて梅を漬ける
・梅酒、梅サワーなど
梅を漬ける上で大事なことは、
「液体に梅が浸かっている」という状態。
梅は液体に浸かっていると
傷みにくいのです。
(イ)の場合
漬け込んだばかりのときには液体がない。
時間をかけてじわじわと梅酢を抽出させて
梅自体がそのうち梅酢にひたひたに漬かる
ようになる。
→梅が液体に浸かるまで時間がかかる。
とくに梅干しの場合、早く多くの梅酢が
出ることがとても重要。
梅シロップは入れる砂糖の量が多いため、
比較的早く梅酢を引き出すことができる。
どちらも梅酢を多く含有しているであろう
少し大きめサイズの梅が好ましい。
適したサイズはL~3Lくらいかな。
(ロ)の場合
はじめから液体にどっぷり浸かっている。
そのため失敗が少なく作りやすい。
梅酒や梅サワーなどは、
梅に対して液体の量が多いので
果汁(梅酢)の量を気にする必要はない。
けれども梅のエキスを充分引き出した方が
美味しいので、やはり果汁の多い大きめ
サイズの方がいいということになります。
適したサイズは2L以上かな。
作りやすいということと、
美味しく作りたいということ。
この両方を思えば、大きめの梅の方が
好まれるということですね。
梅の大きさによって何が違う
さきほどまでは、
梅のサイズによって作りやすさが違うよ~
という話をしていましたが…
では梅の大きさによって、
梅はどう違うのでしょうか?
単に梅が大きい小さいという話ではなく、
具体的な部分を見てみることにしましょう。
なお「小梅」は、単に小さい梅という
ものではなく品種が違うものなので、
普通の梅とは区別して捉えておきましょう。
小さい梅
小さい梅というのは、
- 小さいので果肉が少ない
- 果肉が少ないので梅酢が少ない
- 未熟果(未熟な実)の場合がある
未熟果とは、まだ種がしっかりと形成
されていない、未熟な状態の梅のこと。
梅酢がうまく出なかったり、
傷みやすいことなどがあります。
未熟果を避けるためには、
5月早々に出始めた梅は焦って買わず、
少々待つとよいようです。
ただし梅にも地域差があるので、
出始めの時期は、梅の産地ごとに
気にして見ておくといいでしょう。
なお、未熟果はいけないということではなく
梅酢を必要とする場合には不向きである
ということです。
カリカリ梅などを漬ける場合には、
未熟果が推奨されます。
大きい梅
大きい梅というのは、
- 大きいので果肉が多い
- 果肉が多いため梅酢が多い
- 未熟果の可能性は低い
- あまり大きいものは皮が薄い
大きくて果肉が厚い梅で梅酒を作ると、
とても食べごたえのある梅酒の梅が
できますね~^^
単純に考えると、大きければ大きい梅ほど
果肉が厚いと思いますよね。
しかしなかなかそうはいかないものです。
そもそも果肉の厚みは、
大きさに比例しないのですよ~。
種が大きいもの、小さいもの
梅を食べたときに意外と種が大きく、
果肉が薄いなと感じることがありますよね。
同じ大きさの梅でも、
種が大きいと果肉は薄く、
種が小さいと果肉は厚くなります。
これは梅の品種によっても
ずいぶんと違いがあるようです。
梅の品種は数百あるといわれており、
とても多いので一概にどうとは言えない
のですが…
たとえば有名な「南高梅」は、
サイズが違っていても
種の大きさはだいたい同じ。
実が大きいほど肉厚だといいます。
そして「白加賀」という品種は、
種が小さく果肉が厚いようです。
ブランド梅として売られているものは
品種の傾向などもわかりやすいのですが、
一般に売られている多くの梅は、
品種などの表記もなく、ただ「梅」とだけ
書かれているものも多いのですよね。
ウチは品種とかにこだわらないので、
地物の梅が出ているならばそれを選びます。
やはり時々、サイズは手頃でも種が大きくて
実が少ない…なんてものもありますよ。
それはたいてい出来上がってから
食べてみて初めて気づくことになるのです。
そんなときはちょっとがっかりしますよね。
口にして噛んだらすぐに、
ガチッと種が当たる。
ありゃ…っと拍子抜けです。
買ってすぐに実を割ってみるか、
漬け終わって食べるときにしか
わからないですからね。
何事も経験です(笑)
サイズが違えば作業量も違う
梅を漬ける作業時においても、
サイズによって少々手間が変わってきます。
小さい梅の作業量
小さい梅の作業量は
- 数が多くて大変
同じ重量の梅でも、小さいサイズの場合には
大きいサイズの梅よりも数が多くなります。
極端なところで比較してみると、
その違いはよくわかります。
(例一) 2kgの梅の場合
・Sサイズの梅は約200個
・4Lサイズの梅は約46個
ちょっと例が極端過ぎましたか(笑)
しかし実際、かなりの違いがあるものです。
(例二) 2kgの梅の場合
・Lサイズの梅は約104個
・2Lサイズの梅は約84個
梅の個数はあくまでも目安ですが、
サイズがひとつ違うだけでも
20個くらいの差がありますよね。
小さいサイズだと数が多いのは嬉しい
のですが、とにかく作業量も増えます。
数の多さがそのまま作業量になるのは、
梅は一粒ずつヘタを取ったりするからです。
なかにはヘタを取らずに漬け込むという人も
いますが、これは好みによります。
さらに梅シロップなどを作ろうものなら、
全ての実に穴を開けたりする作業も追加され
ますから、手間は数ほど増えるわけです。
大きい梅の作業量
大きい梅の作業量は、
- 数が少ないので楽
大きいサイズの梅は、
同じ重さの小さい梅よりも数が少ないので
作業量が少なくて楽です。
梅が2kgの場合で、
3Lサイズの梅は60個くらい。
4Lサイズの場合は46個くらいしかないので、
あっという間に終わります。
Mとか2Lサイズで漬け慣れていると、
大きいサイズは拍子抜けするくらいに
すぐ漬け終わりますよ~。
どのサイズが漬けやすいのか
何を作るのかにもよりますが…
梅のサイズによっては、漬けやすいとか
漬けにくいとかの違いがあります。
大きさによっては漬けづらい
(1)小さいサイズの梅
◇ 漬けやすさ
- 容器に入れやすいので漬込みやすい
◇ 漬けづらさ
- そもそも小さいので梅酢が少ない
- 梅の重さが軽いので梅酢が上がりにくい
(梅干しで重石をしない場合)
(2)大きめサイズの梅
◇ 漬けやすさ
- 梅酢が多い
- 梅の重みがあるので梅酢が出やすい
◇ 漬けづらさ(容器に入れる場合)
- 梅と梅の間が広く空き、容器に入れにくい
(3)大きすぎるサイズの梅(4L以上)
◇ 漬けやすさ
- 梅酢が豊富に出る
◇ 漬けづらさ(容器に入れる場合)
- 液体で漬けても梅の嵩が大きくはみ出す
- 大きすぎて容器に入り切らないことも
- 梅同士の隙間が大きく梅酢を抽出しにくい
(梅干しで重石をしない場合)
なんにしても、良し悪しはありますよね。
大きすぎると漬けづらい
さきほどの(3)についての補足です。
(3)大きすぎるサイズの梅(4L以上)の場合。
たいがい大きいサイズを選べば間違いない!
とは思うのですが…
先程記述したように、じつは大きすぎても
漬けづらい!ということがあるのです。
大きいといっても3Lくらいなら
まだいいけれど、4L以上ともなると
ちょっと大きすぎるなぁという感じですね。
梅はほぼ丸いので、大きすぎると
容器に入れたときに梅と梅との空間が
大きくなります。
すると容器の容量を圧迫して入り切らない
ため、ひとまわり大きい容器にするか、
分けて漬けるということになります。
また、梅が大きすぎると
材料の塩などが梅の間に留まりにくく、
隙間から容器の底へ落ちてしまう。
そのため梅酢を抽出しづらいので、
とくに梅干しを容器で漬けるときには
注意が必要です。
梅酒や梅の酢漬け(梅サワー)などの
多くの液体を入れる漬け方の場合には、
梅が液体から大きくはみ出してしまうため、
漬け始めからしばらくは梅をよくなじませて
梅が傷まないよう気を配る必要があります。
そういったことで、
梅を漬けること自体が初めてなら、
あまり大きすぎて漬けづらい梅よりは
お手頃なL、2L、3Lくらいまでのサイズが
漬けやすいでしょう。
まとめ
梅のサイズを選ぶ基準は
・ある程度大きめのサイズがいい
・あとはお好みでどうぞ~^^
ある程度の大きめサイズというのは、
だいたいLか2L、3Lくらい。
大きさが手頃で果汁(梅酢)も多いので、
初めて梅を漬けるならこのくらいのサイズが
漬けやすいでしょう。
4Lになるとかなり大きいので
ちょっと漬けづらくなります。
大きめサイズの梅がいいとは書いたけど、
小さい梅がよくないという意味ではないの
ですよ。
私が手頃で食べやすいと個人的に思う梅は、
小さめから中くらいかな~というサイズ。
だいたいS~Lくらいですかね。
ご飯に添えて食べるには
そのくらいの大きさが適当でいいなと。
これは単なる私の好みですけど。
少々小さめの梅でも、
梅酢は梅にかぶるほど出れば充分なので
たいがいはうまくいくものです。
(水分が抜けていなければね^^;)
いろいろな大きさの梅を漬けてみましたが、
最終的には好みで選んでいいものです。
ただ、ある程度大きめサイズを選ぶほうが
漬けやすいよ~と何度も書いているのは、
初めて梅を漬けて失敗してしまうと
「二度とやらない!」みたいなことになると
勿体無いな~と思うからです。
なので初めて梅を漬ける場合には、
まず漬けやすいサイズで漬けてみる。
そして少々慣れれば、お好みサイズで
漬けてみるというのがいいでしょう。
未熟果については例外で、
カリカリ梅にする以外に向かないので注意。
それでは今回はこのへんで。
どのサイズの梅を選んで漬けるかは、
あなた次第ですよ。
丁度いいサイズの梅ちゃんと
出会えますように~ヽ(´ー`)ノ♪