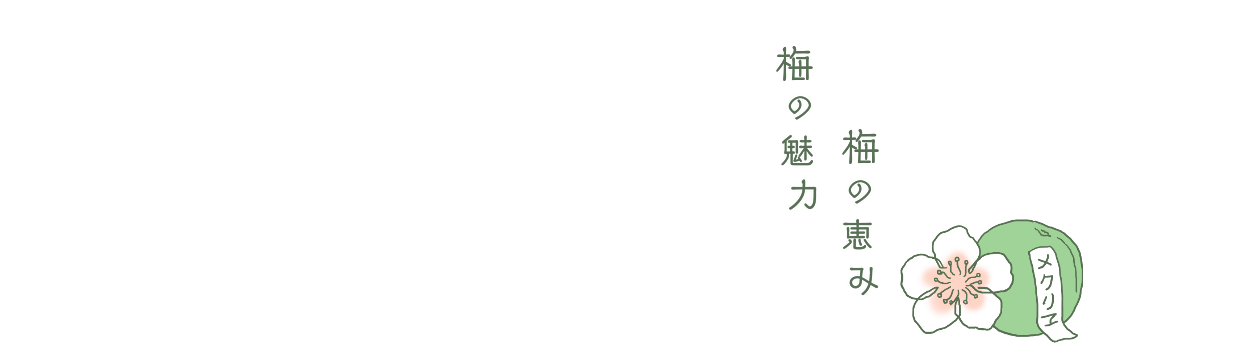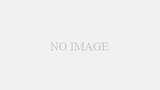この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です。
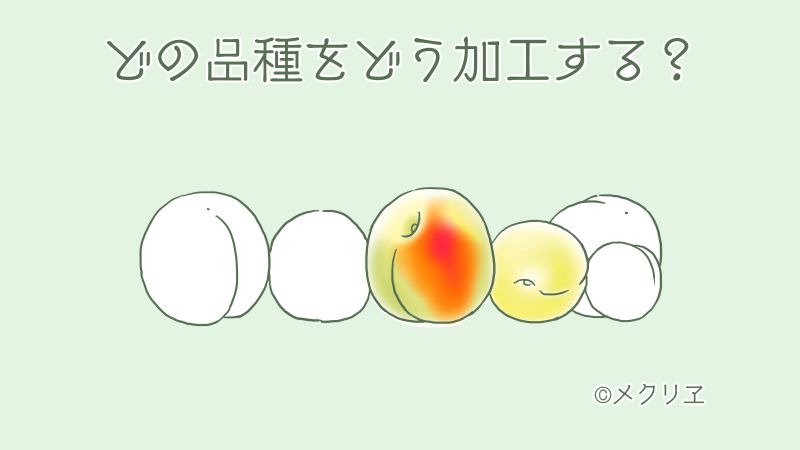
梅を漬けたいなと思うとき。
多くの方はスーパーや通販などで
梅を購入します。
そこで目にするのは、産地と品種。
各地域では地元産の梅が
何かしらあるでしょう。
地元で作っていなければ、
近隣の梅が入荷されることでしょう。
梅の品種というのは
何処にでもある、というものではなく
ある地域で限定的に生産されている品種
というのも多いため、地元で手に入らない
という場合も多いのです。
どうしても品種にこだわりたい場合は
通販で購入するのがいいでしょう。
それにしても梅はあまりに品種が多いので
何を選べばいいのかよくわからないものです。
基本的にはどんな品種でも
どう加工してもいいものなのですが、
なかには、特にある加工に適している品種
というものがあるようです。
ということで今回は、実梅の品種と用途
について調べ、書いていくことにします。
梅の品種で何が違う
梅は昔から各地で植栽されていた歴史もあります。
その土地にあったものが自生していたり、
あるいは品種改良などによって新しい品種が
作られたりすることで、実梅だけで百種類は
あると言われているのです。
梅の品種は沢山あっても、
実際何がどう違うのでしょうか。
一般的には次のようなものです。
- 梅の色(青いとき、熟したとき)
- 実の大きさ、種の大きさ(果肉の厚み)
- 果肉の質(硬さ・質感など)
- 果汁の量(水分量)
- 味の違い(成分の違い)
- 梅の色(青いとき、熟したとき)
青梅の時期には少々わかりにくい
けれど、色の差があるようです。
梅は熟すと黄色くなるものが多く、
赤くなるものが少ない。
そのなかで赤色が差したり
全体に赤くなるのは特定の品種のみ。
また、杏系では果肉が橙色のものもあります。
- 実の大きさ、種の大きさ(果肉の厚み)
実の大きさや種の大きさの違いで
果肉の厚みなどが違う。
- 果肉の質(硬さ・質感など)
果肉の質は、品種によって硬いものや
柔軟なもの、繊維質のものなどがある。
- 果汁の量(水分量)
果汁の量が多いと、梅のエキスが豊富に
使える利点があります。
- 味の違い(成分の違い)
味の違いは、酸味や熟したときの甘みなどの
違い、渋味の有無などがある。
こうした品種の質の違いによって、
特定の加工に向いているとされる品種が
あるのです。
ただしスーパーなどの店頭で、
梅干し用、梅酒用と記載されているのは
単に熟しているか青梅かという違いで
用途を表示していることもあるので、
気になる場合はお店の人に確認してみるのも
いいかもしれないですね。
品種が生まれるとき
梅の品種は、どうやって生まれているのか。
自然発生的に生まれたものもあれば、
人の手を介して作られたものもあります。
- 偶発実生(ぐうはつみしょう)
- 掛け合わせ(交雑あるいは交配)
- 枝変わり(突然変異)
偶発実生というのは、
人為的ではなく偶然に自然発生した実。
掛け合わせは、梅の花に別の花粉を合わせる
ことで生み出すもの。
梅と別品種の梅の花粉や、杏やスモモなどを
合わせた交雑品種などもある。
梅の場合、自家受精(自分の花粉で受精する
こと)ができない品種も多く、
他家受精(別の木の花粉で受精すること)が
殆どのため、自然に品種が混ざることも
あるようです。
そして枝変わりとは、
突然変異で別の特性を持つ枝が出たもの。
増やす方法としては、種からであったり
挿し木や接ぎ木などで増やします。
品種に適した梅の加工
梅の実は品種ごとにそれぞれ特長があります。
その特長が生かされる加工を
推奨されている品種もある。
たとえば「梅干し用優良品種」とか
「梅酒に最適」だとか。
梅の加工というといろいろあるけれど、
代表されるのは梅干しと梅酒。
それとカリカリ梅でしょうか。
あと、近年話題に登ることが多いのは
梅シロップ。
あとはだいたい「梅漬け」とひとくくりに
されることが多い印象です。
そもそも梅で何を作るのか、
品種であまり限定して考えなくても
いいとは思います。
品種にこだわらず好きなように加工すれば
いいのだけれど、推奨されるもので作って
みるのもまた一興。
ということで、加工に対して
推奨される品種を次の項目にまとめました。
ついでに主な産地も加えておきます。
少々偏りがあるかもしれないですが、
参考までにどうぞ。
なお、梅の実の旬は、
5月中旬~6月下旬頃が目安。
小梅は早く、青梅は中間、熟した梅は
遅い時期だと思っておきましょう。
ただし、品種により時期が早い~遅いものが
あり、地域によっても前後するので
注意しておきましょう。
カリカリ梅
カリカリ梅に使われるのは、
小梅や小ぶりの梅が多い。
実が厚く硬めのものが適しており、
収獲は未熟なうちが望ましいとされる。
- 前沢小梅/ 宮城・大分
- 甲州最小/ 熊本・島根ほか1府11県
- 甲州小梅/ 山梨ほか11県
- 竜峡(りゅうきょう)小梅/ 長野ほか14県
- 吉村小梅(飯田小梅)/ 長野
- 鶯宿(おうしゅく)/ 徳島・奈良・大分
ほか1都1府16県 - 紅養老(べにようろう)/ 群馬
などなど。
梅酒と梅シロップ
梅酒に向くとされるのは、
肉厚で種が小さいもの。
梅のエキス(果汁)が豊富に含まれており、
実がしっかりとしていることなどが望まれる。
また、新鮮な青梅で漬けるのがいい
とされます。
梅酒もどんな品種でも作れるのですが
あえて梅酒にといわれるものを記載。
また、梅酒に向いている梅というのは、
梅シロップ(ジュース)にも向いています。
- 鶯宿(おうしゅく)/ 徳島・奈良・大分
ほか1都1府16県 - 剣先(けんさき)/ 福井
- 古城(ごじろ)/ 和歌山ほか7県
- 藤五郎(とうごろう)/ 新潟・秋田・宮城
ほか5県 - 梅郷(ばいごう)/ 群馬ほか1都5県
- 白加賀(しろかが)/ 群馬・埼玉・宮城
ほか1都1府32県
などなど。
他に変わり種としては、次の品種。
紅い(ピンク)色の梅酒ができあがる。
- パープルクイーン(小梅)/ 和歌山
- 露茜(つゆあかね)/ 和歌山・大分・茨城・熊本
これらは記載している産地でしか栽培されて
いないようですが、通販もあるようですし、
取り扱うスーパーもあるようです。
梅干し
梅干しに向いているとされるのは、
果肉が厚く種が小さいもの。
そして、皮が薄くて柔らかいもの
などが挙げられる。
梅干し向きといわれる梅は沢山あるけれど、
そのなかでも特にといわれるものを
記載しました。
梅干しを柔らかく漬けるためには、
熟した梅が推奨されます。
- 白王(小梅)/ 和歌山・高知
- 信濃小梅/ 大分・徳島・長野
- 新平太夫(しんへいだゆう)/ 福井
- 越の梅/ 新潟・宮城・秋田
- 改良内田/ 和歌山・静岡・鹿児島・愛知
ほか3県 - 紅映(べにさし)/ 福井ほか3県
- 十郎(じゅうろう)/ 神奈川・埼玉
- 節田(せつだ)/ 山形・青森
- 谷沢梅(やさわうめ)/ 山形
- 南高(なんこう)/ 和歌山ほか1都2府33県
以上、いくつか挙げてみました。
実際はもっと多くの種類があり、それぞれの
加工に適したものもあるでしょう。
そしてそれぞれ好みというものもあるので、
これらに限らずお好みで試してみるといいでしょう。
品種の差
梅の品種によって、できあがりに
どのくらい違いがでるものか…
というとやはり、多くの差があるものです。
同じように梅干しを作ってみても、
品種が違えば結果は違うものになります。
たとえば梅干し。
〔向いている梅〕
- 皮も果肉も柔らかく、肉厚でしっとり仕上がる。
〔向いていないであろう梅〕
- 皮は厚く硬く、種が大きく実は少ない。
ちょっとあまりに極端な例ですけどね。
やはりどちらかというと
果肉は厚めがいいし柔らかいほうがいい。
実際食べてみても、種でかいな!と
思ってしまうものもありますしね。
しかしまぁ、滅多にそんな極端なことには
ならないので、品種を選ばなくてもたいがい
それなりにいい感じの梅干しは出来上がりますよ。
あとは、青梅を使う場合。
渋味の有無などもあります。
(品種というより若すぎる梅も渋いです)
渋味が強めの梅で作る場合と、
そうでない梅で作る場合。
通常は3ヶ月漬ければ
おいしく食べられるような加工でも、
渋めの梅で作ると渋味が強いために
倍の期間漬けておかなければ
食べられなかったというものもありました。
しかしこれも面白いもの。
梅のいいところは、
時間が経てばそれなりに味が丸くなり
食べやすくなるというところ。
味見をして、渋いと思ったら
寝かせておけばいいのですよ。
これも極端な話なんですけどね。
ウチで経験した渋めの梅は、
人の手があまり入っていない梅を
いただいたものだったので、
通常は市場には出回らないもの。
市販の梅ならば、極端なものはあまりないと
思うので、こだわりが強くないならば
品種を選ぼうとしなくてもいい気もします。
特定の品種を選ぶかどうかは好きずき。
梅の品種にこだわって漬けるもよし、
あまり気にせず漬けるもよし。
品種によって味わいもそれぞれ違ってくる
ので、いろいろ試してみるといいでしょう。
後記
さて今回は、梅の品種と適している加工
について調べて書いてみました。
私のおすすめはやはり
地元で流通しているもの。
なぜ地元のものがいいのかといえば、
やはり鮮度の問題。
梅酒や梅シロップなど、新鮮な青梅で
漬けるものはやはり早いうちがいい。
遠方の梅は運送に時間がかかってしまうので
地元の梅があればそれに越したことは
ないでしょう。
地元の梅で目的の品種があれば一番いいですね。
うちの地元の場合、特に品種の記載なく
売られているものが多いので、
あまり品種を気にしていないのです。
品種の特定ができない雑種なのかなぁ~
なんて思いながら漬けていて、こんな感じ
でも梅干しは普通に柔らかく仕上がります。
それでも南高梅は入荷されるので、
お手頃価格のときには南高梅で梅干しを
作ることもあります。
すると、やはり違うな!と思うこともあり。
しかし肉厚の南高梅は、
青いうちに梅酒にする方が好きですね。
私は飲みより梅の実を食べる方なので…。
好みはいろいろ。
基本的には、好きなものを好きな加工方法で
楽しんでいきましょう。
それでは今回はこのへんで。
ここまでお付き合いくださいまして
ありがとうございます。
あなたの好みの品種が
見つかるといいですねヽ(´ー`)ノ