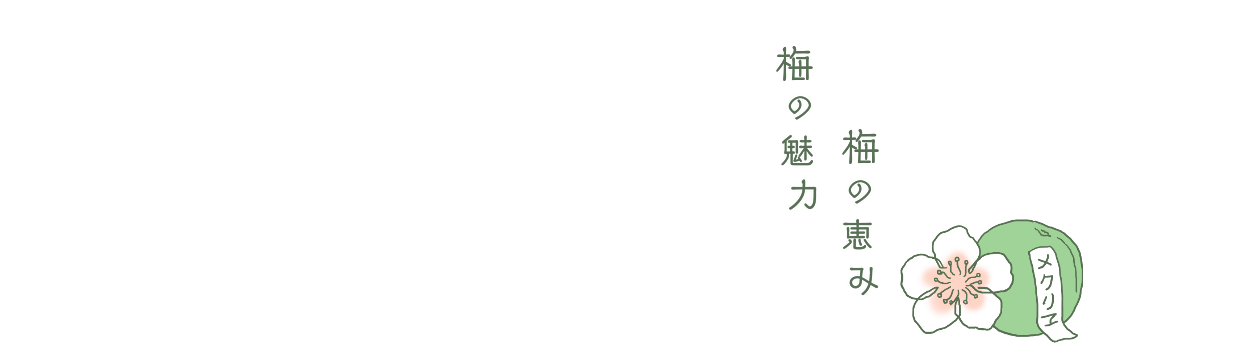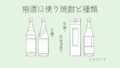この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です。
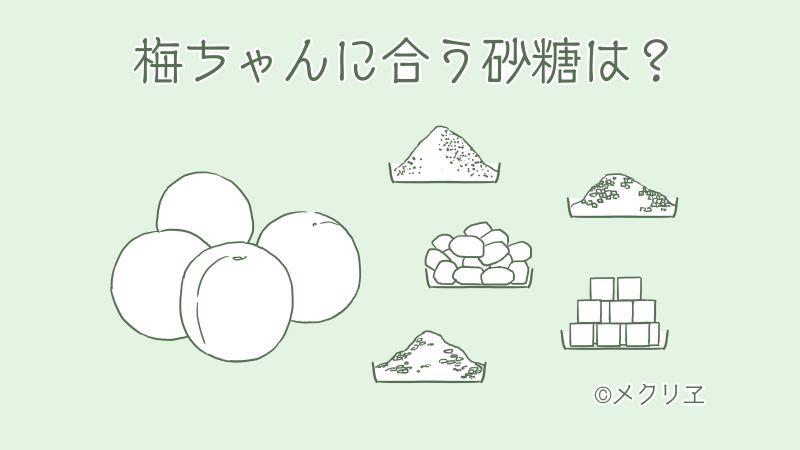
梅シロップを作るときに気になるのは、
砂糖のこと。
氷砂糖がいいっていうけど、なんでなの。
他の砂糖ではだめなのかな。
まずは砂糖の種類に悩む。
そして、
けっこう使う砂糖って多いんだよね…。
減らしちゃだめかな。
と、砂糖の量に悩む。
さらに次には、
砂糖が下に溜まって固まってる…
砂糖が溶けずに悩んじゃう。
はじめて漬けるときには、いろいろ不安。
悩みは尽きないですよね。
今回はそんな、梅シロップの砂糖に
まつわることについて書いていきます。
それではいってみましょ~。
梅シロップに使う砂糖の種類
梅シロップに使う砂糖には定番があります。
それはもちろん、氷砂糖。
その他にも、いろいろな種類の砂糖を使う
レシピが出回っているのですが、
そのなかで多いのは上白糖などでしょうか。
他にはグラニュー糖や三温糖、
キビ糖やてんさい糖など、
それぞれに好きな砂糖を使っている
といった感じですよね。
では定番の氷砂糖と、その他の砂糖とでは
どうちがうのでしょうか。
氷砂糖
梅シロップに定番なのは氷砂糖。
氷砂糖が一般的にいいとされ、
よく使われています。
その理由はなんでしょう。
氷砂糖は大きな結晶になっている砂糖。
ゴツゴツとしていて、
梅と接触するのは一部分。
氷砂糖は、じわじわゆっくり溶ける性質が
ある。
このゆっくり速度が、梅などの果実から
エキスを抽出するのに丁度よく、
果実酒を漬けるときにもよく用いられて
いるのです。
これは梅シロップでも同様で、
ゆっくりと梅のエキスを抽出するために
向いているといわれています。
初めて梅シロップを作る場合には、
まずは定番の材料と分量で漬けてみるのが
いいですよ。
アレンジはその次から。
さらさらの砂糖
では、普通のさらさらとした
粒の細かい砂糖ではどうなのでしょう。
さらさらの粒の細かい砂糖は、
沢山の梅の隙間にも入り込んで
梅全体を覆ってまとわりつきます。
すると砂糖の浸透圧で、
梅の水分を一気に奪ってしまうのです。
一見、早くシロップが出来上がるように
思えますが、梅の成分はあまり抽出されず、
風味の少ないシロップとなってしまうようです。
梅を食べるのが目的ならば、
これでもいいでしょう。
しかし梅シロップは、シロップをドリンク
として使う目的で作ります。
シロップだけ使うというのなら、
なんだかもったいないですよね。
出来上がりが早ければいいというものでは
ない、ということなのでしょう。
しかしそれでも、
氷砂糖よりも粒の細かい砂糖がいい、
という場合もあるようです。
さらさら砂糖の利点?
さらさらの粒の細かい砂糖を使う利点。
それは、梅シロップが早くできるという点。
(梅エキスが出切っていないとしても)
先ほどと言っていることが真逆ですが…笑。
利点を挙げるとすれば、梅が発酵する前に
早く仕上げてしまえば心配いらないよね、
というところだと思います。
しかしさらさらの砂糖を使ったからといって
できあがるまでに発酵しないというわけでは
ないので、条件が揃えばあっというまに
発酵してしまいます。
砂糖にはそれぞれの特徴があり
風味なども違うので、
単にいろいろ楽しみたい、
ということなら好みの砂糖でいいでしょう。
グラニュー糖や白ザラメは、
氷砂糖と同様に純度が高くクセがない。
上白糖はグラニュー糖より甘味が強い。
色のついた砂糖は、コクがあったり
少々クセがあったり。
そしてシロップは黒くなります。
砂糖の量が足りないときには、
別の種類の砂糖を追加してもいいし、
ある程度自由に漬けてみても大丈夫です。
ただし、砂糖の全体量を極端に変えるなどは
しないほうがいいでしょう。
特に、極端に量を減らす場合には、
さいあく、梅が傷んでしまいます。
砂糖の量
砂糖の量については、
少なからず一度は疑問を持つことでしょう。
こんなに多いの…って。
半分にしちゃだめかなぁ…とかね。
私もそうでした。
適度な砂糖の量
砂糖の適量はある程度決まっています。
それは、梅が腐らない程度の量は必要
だということ。
一般的なレシピでは、
梅の重さと砂糖の重さが1:1。
梅が1kgなら、砂糖も1kg。
この量は、だれもが失敗しないための量
だと思います。
砂糖漬けなどで、食品が腐らないための
砂糖の量は、だいたい食品の重量の50%~65%
くらい必要なようです。
なので、70~80%以上入れておくと安心
ということです。
砂糖を少なめにするなら
砂糖を少しでも減らしたいのなら、
酢を添加するなど、代替のものを入れる
ほうがいいでしょう。
酢を入れると発酵もしにくいので、
丁度いいかも。
ただ、当たり前ですが酸味が増します。
酢以外なら、焼酎(35度以上)を5%程度
入れるのもいいでしょう。
ちなみにウチで試したことがある分量は、
次の通り。
- 梅500g
- 砂糖250g
- 酢50g
1:0.5:0.1ですね。
漬けて半年くらいは美味しく食べられます。
1年近く経つと、酸味が増して風味が落ちる…
とメモしていました。
(実をそのまま食べていましたから)
ちなみに保管は冷暗所。
さらに時間を経るとまた風味は変わります。
しかし早めに使いきるのがいいでしょう。
砂糖を多めにするなら
砂糖を多くしたい場合はお好みで、
ある程度増やしてもいいのでは。
ただ、砂糖の量にもよりますが、
砂糖が多いと発酵しやすいことも。
砂糖が多い分には、
保存性については充分でしょう。
また、砂糖を一度に入れると溶けにくいため
分けて入れるほうがいいでしょう。
砂糖が多すぎると、梅の風味もそこそこに
ただただ甘ったるいばかりで砂糖の主張が
強く、使いにくいものになります。
(実施済みですよ~。分量を間違えて…(T_T)
そして、砂糖のとりすぎはよろしくないので
個人的にはまったくおすすめはしないですよ。
砂糖の糖度と甘味度
砂糖の甘さには、
「糖度」と「甘味度」があります。
砂糖の糖度
砂糖でいう糖度とは、砂糖の主成分である
ショ糖の純度についてのこと。
(果物でいう糖度とは違うものです)
つまり「糖度」が高い、というと
ショ糖の純度が高いということ。
糖度が高い順はつぎのとおり。
高い←‖グラニュー糖>氷砂糖>白ザラ糖>中ザラ糖>上白糖>三温糖>きび糖>黒糖‖→低い
角砂糖・粉砂糖はグラニュー糖と同じ。
顆粒状糖はグラニュー糖と氷砂糖の間くらい。
なお、ケーキなどに使われる粉砂糖は、
梅を漬けるには向かない。
砂糖の甘味度
甘味度とは、人の味覚での甘さを示したもの。
糖度とは比例せず、糖度が低いわりに
甘味度が高いものがあります。
その理由は、転化糖とミネラル分によるもの。
- 転化糖
転化糖とは、ショ糖から
果糖とブドウ糖に分解したもの。
この果糖の甘味が強いため、
転化糖はショ糖より甘く感じる。
- ミネラル分(灰分)
ミネラル分は多少苦味を含むのですが、
これとショ糖の甘さとの対比から
より甘く感じるようです。
梅シロップの砂糖が溶けない
梅シロップを漬けるときによく経験すること。
それは、砂糖が容器の底に沈殿してしまい、
溶けないということ。
梅シロップには大量の砂糖を入れて作ります。
徐々に砂糖が溶け出して、
梅を覆うほどのシロップが上がってくる。
容器を揺らすなどして
砂糖を溶かそうとするのですが、
しばらくたっても砂糖が溶け切らない。
容器の底に溜まってしまうと、
固まって溶けにくくなってしまうのですよね。
そんな沈殿した砂糖を溶かす方法は
いくつかあります。
- しつこく揺らす
- 天地を返す
- 道具でかき回す
- 火を入れて溶かす
- 砂糖を分けて入れる
しつこく揺らす
容器ごと、梅シロップを静かに
揺らしてあげます。
ただなんとなく揺らすだけでは
底に溜まった砂糖はなかなか溶けてくれない。
容器を少し傾けて、容器の底のシロップまで
動くように、充分回し揺らしてあげます。
これをしつこく一日数回行います。
そのうち溶けてくれますよ。
天地を返す
天地を返すのは、
しっかり蓋のできる容器の場合に行います。
蓋がちゃんと閉まっているのを確認して、
上下を逆さにするのです。
これを時折やるだけ。
これがいちばん簡単ですね。
道具でかき回す
入れた砂糖が、ある程度は溶けたけれど
底に溜まって固まってしまい、
これ以上はどうしても溶けないんだけど…
と、心配ならやります。
なぜなら、漬けている途中で
あまり蓋を開けたくないから。
使う道具は、菜箸や長いスプーンなど。
きれいに洗って乾いている道具を
アルコールで消毒。
容器の蓋を開けて、容器の底に固まった
砂糖を掘り返すように崩して
やさしく撹拌します。
終わったらきっちり蓋をすること。
強制的にかき回してしまうので、
あっというまに溶け切ります。
火を入れて溶かす
梅のエキスが抽出されて、
そろそろいいかなと思っても
砂糖が容器の底に溶け残っているのなら、
シロップを火にかけて砂糖を溶かします。
生のままのシロップを味わいたいのなら
やはり他の方法で溶かす必要がありますが、
梅シロップを長期間保存するためには
どのみち殺菌のために火にかけるのです。
生にこだわりがなければ、
最終的に火にかけることで
少々の溶け残りは心配いらないでしょう。
砂糖を分けて入れる
そもそも砂糖は、
一度に大量に入れると溶けにくい。
砂糖がなかなか溶けにくい状態にあると、
梅が発酵してしまうこともあるようです。
そこで砂糖を溶けやすくするために、
分量の砂糖を一度に入れるのではなく、
あらかじめいくつかに分けて
順次追加するという方法があります。
分けるのは3~4回くらい。
しかしこの方法であっても、
よく容器を揺らして早く溶かすように
しましょう。
後記
さて今回は、梅シロップを作るときの
砂糖にまつわるあれこれについて
書いてみました。
梅シロップをほかのいろいろな砂糖で
漬けてみるのもありですが、
一番シンプルでスッキリした味わいに
仕上がるのは、
やはり氷砂糖だけで漬けること。
さらさらの砂糖で漬けるのならば、
個人的にはきび糖がおすすめでしょうか。
黒砂糖の場合は独特のクセと風味が強いし、
きび糖よりもシロップが黒くなります。
(これはあたりまえか…)
1年に一時期だけの梅の時期。
一種のお祭りみたいなもの?なので、
一度は基本の氷砂糖で漬けてみて、次からは
好きなように漬けてみるのがいいですよね。
それでは今回はこのへんで。
ここまでお付き合いくださいまして
ありがとうございます。
あなた好みの漬け方が
できるといいですね~ヽ(´ー`)ノ