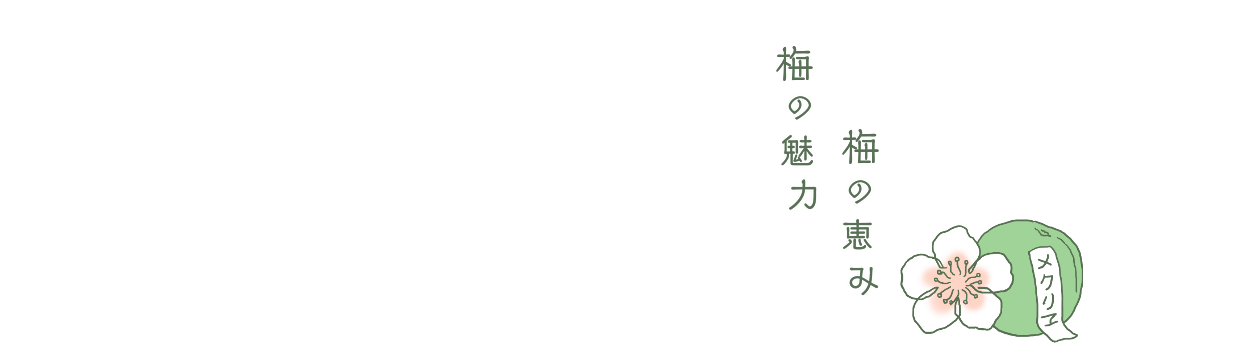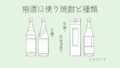この記事を読むのに必要な時間は約 12 分です。
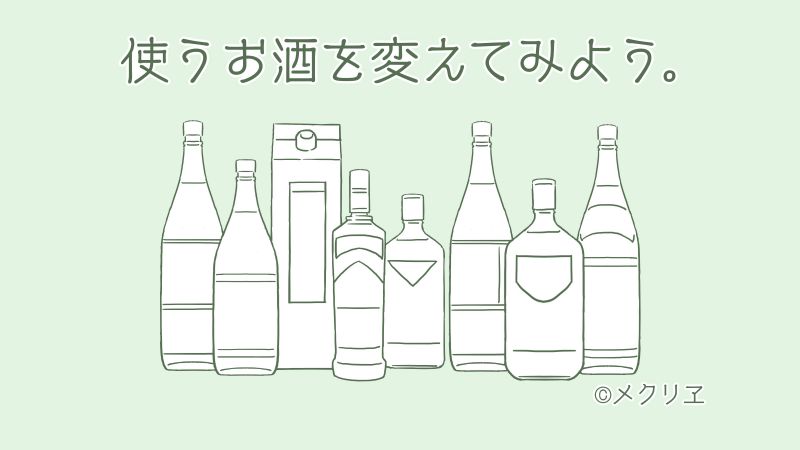
梅酒を漬けるにあたって、
毎年定番の焼酎(ホワイトリカー)ばかりでは
ちょっと物足りない。
たまには違うお酒で漬けてみたいよね~
なんてこともありますよね。
でも特にお酒好きでもないし…
(飲むけど)
どれがいいんだか、さっぱり!
そんなあなた(私)のために、
お酒について調べてみることにしました。
ちなみに私は、日頃から家では
お酒をほとんど飲まない、という状況。
梅酒は3年超えたものが好きで、
気が向いたらほんの少しを割って飲むだけ。
外飲みのときには
ロックで梅酒を頼みますけども。
氷が入ってるので、少し薄まって
ちょうどいいですからね。
他はすっきりした日本酒を好み、
カクテルは結構好きで、ビールは飲めない。
ウイスキーは飲めなくはないけど
美味しいとは思わないし匂いが少し苦手。
そんな私の趣向で書いていきますよ~^^;
梅酒に使うお酒
梅酒はいろいろなお酒を使って
作ることができます。
しかし使っていいお酒と、
使ってはいけないお酒。
そして、合うお酒と
合わないお酒があります。
酒税法を知っておこう
まずは酒税法の一部分ですが、
重要なので知っておきましょう。
日本では基本的に、
個人でお酒を作ることは禁じられています。
では、家で梅酒を作るって違法なの?
というと、そうではなく。
自家醸造については、
規定の範囲内であれば例外として
製造行為とはしないとされています。
つまり自分で飲むために、
酒税が課税されたアルコール分20度以上の
酒類を使って梅酒を漬けるのは、
例外として酒税法違反にはならないのです。
ただし、穀物やぶどうなど、
使ってはいけない材料もありますので
詳しくはこちらへどうぞ。
うっかりぶどうを漬けたり、
アルコール度数20度以下のお酒を使うと
アウト!ということなので
気をつけましょうね。
なお、アルコール度数を表す
「度」と「%」は同様の意味です。
お酒のラベルでアルコール度数を
確認しましょう。
梅酒に合うお酒とは
梅酒に限らずですが、
果実酒を漬けるときにはアルコール度数が
高いほうがいい。
それには2つの理由があります。
- 梅の成分を引き出しやすい
- 長期保存ができる
さらに、梅の風味を活かすならば、
これを邪魔しない無味無臭のお酒がいい。
こういった理由から、
梅酒に使うお酒の定番は
アルコール度数が35度で無味無臭である
焼酎(ホワイトリカー)なのです。
さて、梅酒に使えそうなお酒は
他にどんなものがあるのでしょう。
ここからは、
梅酒に合うか合わないかは別として
お酒の分類と種類とをまとめますので、
梅酒を漬けるときの参考にどうぞ~。
お酒の分類と種類
お酒とは、果実や穀物などを
アルコール発酵させたもの。
果実は、ぶどうやりんご、さくらんぼなど。
穀物類では、米・麦・トウモロコシなど。
そのほかにも、さつま芋やサトウキビ、
蜂蜜など、さまざまなものから作られる。
そして原料は同じでも、
製法の違いによって違うお酒になるのです。
- 醸造酒
原料を発酵させたもの。
日本酒・ビール・ワイン・蜂蜜酒など。
- 蒸留酒(スピリッツ)
醸造酒を蒸留したもので、アルコール分が高い。
焼酎・ジン・ウォッカ、ウィスキーやブランデーなど。
- 混成酒
酒を調合などしたもので、リキュールなど。
意外なところでは、酒税法では味醂(みりん)もここに分類される。
それでは、それぞれを詳しく見ていきます。
醸造酒
果実や穀物などの原料を発酵させたもの。
醸造酒のアルコール度数は低めで、
高くても20度くらいまで。
そのため基本的には、
梅酒の材料としては向かないお酒が多い。
◇ 果実酒
ぶどうやりんごなどの果汁を、
自然発酵させたもの。
ぶどうのお酒はワイン、
りんごはシードルといわれる。
ワインのアルコール度数は、10~15度。
なお、ワインにブランデーを加えた
ポートワイン(酒精強化ワイン)は、
アルコール度数が19~22度。
20度以上のものであれば、
梅酒に使うこともできるでしょう。
◇ ビール
主に大麦の麦芽を原料とし、
ビール酵母で発酵させたもの。
アルコール度数は、5度前後。
もちろん梅酒に使ってはいけない。
◇ 日本酒
主に米と麹を原料とし、発酵させたもの。
酒税法において、
アルコール度数が22度未満のもの。
一般的に販売されているのは
15度前後のものが多い。
これでは梅酒を漬けてはいけない。
日本酒の原酒であっても、
多くは17とか19度であったりするので、
日本酒で梅を漬けるときには
必ず20度以上であることを確認しましょう。
近年では、梅酒用・果実酒用として
アルコール分20~21度の純米原酒などが
販売されています。
日本酒を使いたい場合には
このようなものを選ぶといいでしょう。
蒸留酒(スピリッツ)
醸造酒を蒸留したもので、
スピリッツ(英語)ともいう。
蒸留は、発酵液を熱にかけて蒸発させ、
冷やしてアコール分などを取り出す製法。
これを繰り返し行うことで、
高いアルコール濃度のお酒ができる。
このため、蒸留酒にはアルコール度数が
高めのものが多い。
度数は一番高いもので96度まで。
…もはや危険物ですね…。
ちなみに度数が67度前後から、
危険物に該当することがあるようです。
蒸留酒は色によって
区別されることもあります。
- ホワイトスピリッツ
蒸留時のまま、無色透明なもの。
焼酎、ジン、ウォッカなど。
- ブラウンスピリッツ
蒸留したあと樽で熟成させ、色づいたもの。
ブランデー、ウィスキーなど。
◇ 焼酎
日本で生産される蒸留酒。
アルコール度数は甲類で36度未満、
乙類で45度以下。
- 関連記事:焼酎の種類
焼酎の主流は乙類で、
20~25度数のものが多い。
梅酒を作るときの定番は、甲類焼酎の
ホワイトリカーで、35度あります。
ホワイトリカー以外の焼酎でも
梅を漬けることはできるのですが、
クセの強い焼酎は
梅の風味と合わないものもあるでしょう
◇ ブランデー
果実酒(ワイン)を蒸留したもの。
原料は主にブドウ。
他にりんごやさくらんぼなどもある。
アルコール度数は、40~50度と高い。
ブランデーの中でも
「V.O」は、熟成させた古いもので
アルコール度数は37度。
とても香りがよく、
梅酒づくりにもよく用いられます。
◇ ウィスキー
大麦・ライ麦、トウモロコシなどの穀物を
原料としたもの。
アルコール度数は、40~60度。
◇ ウォッカ(スピリタス)
主に麦などの穀物や、じゃがいもなどを
原料としたもの。
アルコール度数は40~96度とかなり高め。
クセは少なく、無味無臭。
◇ ジン
主に大麦やライ麦、じゃがいもなどを
原料とする。
アルコール度数は、40~50度。
クセは強くない。
◇ ラム
サトウキビを原料として作られる。
アルコール度数は、40~75度。
よく果実酒に用いられ、
梅酒を作るのもよいようです。
◇ テキーラ(メスカル)
リュウゼツラン(竜舌蘭)という
植物の絞り汁から作る。
アルコール度数は、35~55度。
混成酒(再製酒)
醸造酒や蒸留酒を原料に、
果実や香草などで風味を移したり、
混ぜて糖類などを加えるなどして
調整したお酒。
◇ リキュール
蒸留酒に、果実や香草類、
甘味料・着色料などを入れて調整したもの。
カクテルなどに使われる。
アルコール度数は
15~70度くらいと幅広い。
◇ 味醂(みりん)
もち米と米麹に、
焼酎か醸造用アルコールを加えて作られる。
みりんは調味料というイメージが強いが、
そもそもは酒類。
糖分を40~50%くらい含み、
アルコール度数は14度くらい。
カクテルにも使われるようだが、
このままでは梅酒には使えない。
そもそも、梅をみりんに漬けるの?
と思うかもしれないですね。
そのむかし、まぼろしの「みりん梅酒」
というものがありました…笑。
みりんで梅を漬けると、
とてもおいしい梅酒になるようです。
しかし普通の本みりんで梅を漬けると
法律違反になってしまうのですよね…。
そこで、梅酒用に作られた
みりんがありました!
「酒精強化みりん」
純米みりんに本格焼酎を加えることで、
アルコール分を20~21度にしたもの。
みりんはそもそも半分くらいは糖分なので、
梅を漬けるときには、
甘味類の添加は一切要らないようです。
ちょっと変わり種ですが、
一度は試してみたいものですね。
後記
今回は、梅酒に使うお酒を選ぶために、
お酒の種類について調べてみました。
ウチではずっと、梅酒はホワイトリカーで
漬けていたのです。
けれども独特のアルコール臭が
いつもキツいと感じていました。
それで毎回、3年を超えてから梅を食べたり
梅酒を飲んだりしていたのです。
そんななか、知人の勧めで
ブランデーのV.Oを使うことに。
それまではブランデーというと、
強いお酒で香りがキツイ、
というイメージだけがあったのですけど、
どうやら食わず嫌い?だったようで。
とてもいい香りで、満足。
そしてラム酒で漬けることも勧められ、
これはまだ漬けそこねているのですけれど
来年こそはラムで挑戦しますよ。
ウチはお酒というよりも、
漬けた梅の実を食べるのが楽しみで
漬けています。
もちろんお酒も飲みますけど…ちびちびね。
そうして十年超えの梅酒が
熟成されるのです…笑。
それでは今回はこのへんで。
ここまでお付き合いくださいまして
ありがとうございます。
梅酒に使うお酒を
たまには変えて楽しみましょ~ヽ(´ー`)ノ