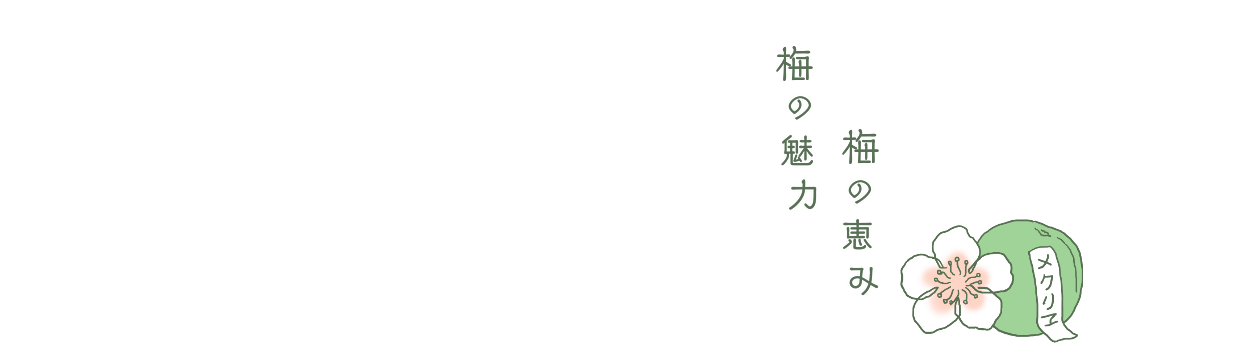この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です。

梅の味噌漬け(梅味噌)を仕込んで
しばらくすると、…あれ?
こんなことはないでしょうか。
- 味噌がふつふつとしている
- 妙に味噌の嵩が増している
- 味噌と梅の香りが充満している…
しまいには、梅味噌が容器から溢れ出した!
なんてまぁ…ここまでは極端ですが…
(詰め込みすぎた末に経験アリです^^;)
こんな状態になったとき、
梅味噌は発酵しています。
静かにじわじわと発酵していることもあれば
ボコボコと泡立つように過剰に発酵する
こともあり。
どのみち梅味噌は発酵しやすいようです。
今回はそんな、梅味噌の発酵について
書いていきますよ~。
梅の味噌漬けは発酵する
梅味噌は発酵するのですが、
必ずというわけでもなさそうです。
では、どんな状態にあるものが
発酵しやすいのでしょう。
〔発酵しやすい条件は?〕
よくいわれるのは、梅の熟度。
梅が熟していると糖度が高いため
発酵しやすい。
また、味噌の状態にもよるようです。
梅味噌が発酵するのは、
酵母の働きによるもの。
酵母はどこにでもいる菌。
果実にも存在し、
もちろん梅にも存在している。
酵母菌は糖があるところで活動する。
酵母菌が糖を食べて分解することで、
発酵が進むのです。
丁度いい糖分と適温であれば、
酵母菌は活発になる。
梅味噌を漬ける材料として砂糖も入れる。
発酵する条件としては申し分なし、
というところでしょうか。
砂糖の量や種類の他、
自家製味噌などでも発酵しやすい。
結局のところ青梅でも黄熟した梅でも、
発酵するときにはするのですよね。
発酵させない・させる
梅味噌の発酵については、賛否両論。
発酵の兆候がないうちに、
火にかけて仕上げてしまうレシピ。
しばらく発酵させてから、
発酵止めをして仕上げるというレシピ。
どちらもある。
梅味噌は、梅と味噌が混ざりあった
とてもいい香りがするのですが、
発酵したらいけない、と思ってしまうのは、
発酵が進むと強いアルコール臭がしてくる
ということからでしょう。
しかし発酵はいいこともある。
発酵とは、微生物が物質を分解して、
人に有益な状態に変えてくれること。
発酵によって美味しくなったり、
栄養成分が増えたり、消化吸収しやすく
してくれたりする。
発酵ブームがあるように、
発酵はやはり体にいいらしい。
ただ、発酵も過剰になると
味や風味が劣化してしまうので
注意が必要です。
梅味噌を漬けてからの変化と発酵
発酵がこわい、と思うと
いろいろ心配になりますよね。
そこで、次のことをざっと書いておきます。
- 梅味噌を漬けてからの変化
- 発酵時の状態と対応
梅味噌を漬けてからの変化
梅味噌を漬けてからの変化は次のとおり。
(※何事もない場合)
- 梅味噌を漬け込み
↓ - しばらくは味噌が硬く、変化なし
↓ - 梅から水分、エキスが染み出る
↓ - 味噌が梅の水分で柔らかくなる
↓ - 味噌全体がトロトロとしてくる
ここまでにかかる期間は、
気温や材料・分量によっても違います。
発酵時の状態と対応
発酵するタイミングはいろいろ。
漬け込んですぐの早い段階で
発酵することもあれば、
数週間後に発酵することもあり。
また、特に発酵しないまま
(気づかない程度?)のこともある。
〔発酵の兆候〕
- やたら味噌と梅の匂いが漂う
- 見た目ポコポコとしている
- 一気にどろどろに液状化する
- 全体が盛り上がる(過剰発酵)
少しずつ発酵しているようなら
様子を見守る。
日に一度程度は
全体をかき回したほうがいいようです。
私は瓶を少々揺らす程度にしていますけど。
しばらくして発酵が治まることもあるけれど
あまり置くと風味が落ちてくる。
少量なら早めに使い切るのもよし。
しばらく置くのなら、冷蔵保存。
あるいは火入れをして発酵を止めてしまい、
涼しい場所に置くか冷蔵保存します。
過剰に発酵してもそのうち収まりますが、
あっという間にアルコール臭がしてくるし
味も劣化してしまいますので、
早めに火入れをしてしまうほうが
いいでしょう。
少々アルコール臭がしても
火にかけることによって匂いは飛びます。
ただ、放置がすぎるとやはり残りますよ。
もうだめだと諦めないで、
火入れをすることで充分使えるし
熟成するとまた違った味を楽しめます。
- 関連記事:梅味噌の作り方~梅味噌の保存
味噌の状態
味噌はそもそも発酵食品。
味噌の状態によっては発酵しやすい。
市販の味噌の種類はいろいろですが、
味噌の発酵を止めてあるのかどうか
というのもいろいろ。
市販の味噌は主に
次のような状態で売られています。
〔常温で販売されている味噌〕
- ガス抜き用の容器(※1)に入れてある
- 発酵止め(※2)をしてある
〔冷蔵で販売されている味噌〕
- 発酵止めをしていない
※1:「ガス抜き用の容器」
ガスが溜まって容器が膨らまないように
ガスが抜ける特殊なパッケージに
入れてあるもの。
※2:「発酵止め」については次のとおり。
- アルコールを添加している
- 火入れをしてある
「アルコールを添加」するのは、
菌の性質を利用して極力活動を抑え
(あるいは殺菌して)発酵を止めるため。
この場合、原材料表示に
「酒精(アルコール)」などと記載がある。
「火入れ」の場合、
酵母などの菌は高温に弱いため、
火にかけることで殺菌をして
発酵を止めるもの。
冷蔵保存の場合は温度が低いために、
菌の活動を抑えられている。
つまり、酵母が生きているのかなと
思われるものは、
- 常温でガス抜き用の容器に入れてある味噌
- 冷蔵で販売されている味噌
ということになります。
菌が生きている味噌を使い、
常温で梅や砂糖を入れ込んだらどうなるか。
(それでもちゃんと作れますよ)
ともかく使う味噌によって、
発酵するかどうかや発酵するタイミング
などは変わってくる、ということです。
- 関連記事:梅に使う味噌の種類を選ぶ
ちなみに使う砂糖によっても、
発酵のしやすさは違うようです。
まぁ、発酵してもそんなに支障はないので
こわがらずにいろいろと
試してみるといいでしょう。
後記
今回は梅味噌の発酵について
書いてみました。
結局のところ、梅味噌は発酵するもの
と思っている方がいいのでしょう。
微妙に発酵しても慌てず、
かき回しつつ様子を見る。
最終的には火入れをして、冷蔵保存する。
この流れが当たり前だと思えば、
発酵してもこわくはないですよ。
梅味噌が発酵しても、
容器からこぼれなければ
あまり気にならないのですけど。
容器から吹き出してしまうと、
大惨事のように感じてしまいます。
以前ウチで昼間に漬けた梅味噌が、
夜には容器から吹き出ていた
ということがありました(笑)
梅味噌を漬けるときには、
少し余裕のある容器で漬けたほうが
いいですね。
それでは今回は、このへんで。
ここまでお付き合いくださいまして
ありがとうございます。
もう梅味噌の発酵は
こわくないよ~ヽ(´ー`)ノ